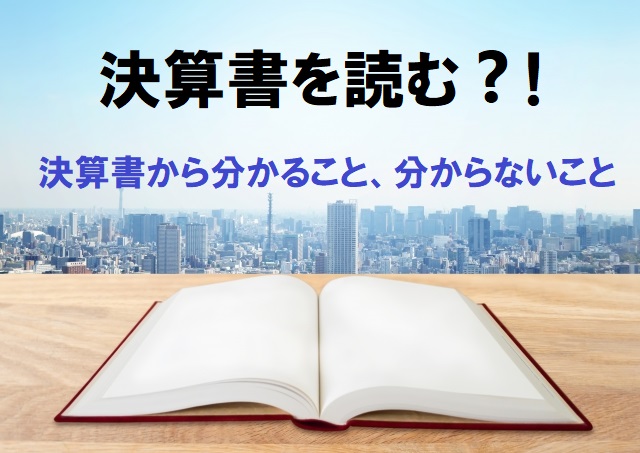こんにちは、 SunnyBizコンサル です。
みなさんは普段、本を読みますか?
本は、読み物として手に取ります。
では「決算書」を手にして「よし!読むぞ!!」と思いますか?
ほとんどの方が、決算書はそこそこに見るもの…という感覚ではないでしょうか。
もはや利益だけ確認して「ほうほう…。」と思っている方もいるかもしれませんね。
企業経営に関わっていると、「決算書を読もう!」「決算書の読み方」というフレーズを見聞きすることがあると思います。
そういうタイトルの書籍も数多く出ており、気になっている方も多いのではないでしょうか。
ただ、文章が書かれているならまだしも、数字が羅列してあるものを読むって……
一体どういうことなの?って思いませんか?
今回は、決算書を具体的に読み込むスキルをつける前に、「決算書を読む」ということはそもそもどういう事を言っているのか、そのポイントを解説します。
要点はコチラ。
- 決算書には何が書かれているのだろう
- 決算書で何が分かるの?
- 決算書では分からない事もある?
まずは決算書を読むということが一体どういうことなのか、概要を掴んでおきましょう。

決算書を読むとは?

決算書に書かれている事を知ろう
企業は毎年、1年間に行ったさまざまな活動、取引を集計してその結果を決算書にとりまとめます。
決算書のうち、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の3つを読めば、その企業の実情をほぼ把握することができます。

この財務三表には、企業がどのようにお金を集め、何に使い、どうやって、どれだけ儲けた(損した)のかが記載されています。
また、手許の現金・預金残高や、土地・建物などの保有状況なども載ってくるため、どれだけの財産を持っているのか?ということも把握することができます。
さらに、これから入ってくるお金、支払うべきお金など、お金の出入りも確認することができるため、資金繰りも知ることができます。
決算書は企業の事業活動と実態を集約したものであり、企業の実情を表す成績表といえる重要資料です。
決算書から分かることとは?
先に触れた通り、財務三表には企業がどのようにお金を集め、何に使い、どうやって、どれだけ儲けた(損した)のかが載っています。
財務三表はそれぞれに特徴があり、3つの表は密接に関わっています。
ひとつひとつを読み解くことも大切ですが、3つを組み合わせて読む方がより詳しく情報を得ることができます。
外から見ると大きく儲かっているように見える企業であっても、しっかりと内部を見ないとその実態を把握することはできません。
財務三表を組み合わせて見ることで、業績はもちろんのこと、企業を取り巻く環境に変化がないか?数字に矛盾が無いか?異常な金額がないか?といったことも確認できます。
そして決算書を網羅して見ていくと、その企業が儲かっているか?倒産しないか?成長していくのか?といった企業の実情と展望を読み解くことができます。

決算書は「収益性」「安全性」「成長性」の3つの視点で読み解くことができ、それを分析することにより、企業の活動実態が分かるということになります。
決算書から分かる経営の姿

決算書からは、企業の「収益性」「安全性」「成長性」を見る事ができます。
収益性とは
収益性とは、儲ける力があるか?ということです。
儲けとは利益のことであり、一般的に利益が出ていると儲けているといえます。
企業は、商品やサービスを生み出す際に資金を投下します。
そして出来上がったものが市場で価値あるものと認められ、投下した資金以上に回収することができれば、それは利益を生み出す事業として成立します。
ただし、利益を生み出す力は永遠とは限りません。
投下資金をしっかりと回収し続けるだけの商品力、機能、品質、価値、ニーズがあるか?という点で、社会的に価値を生み出し続ける力があるかどうかが重要となります。
収益性の分析は、投下した資金に対してどれだけの利益をあげていくか?ということです。
企業の資金をより効率的に儲けへ繋げることが求められ、収益性を高めるためには、ムダを排除することや、コスト管理も大切なこととなります。
要するに、収益性の分析は、投資の効率を見ることと言えます。
安全性とは
安全性とは、倒産の恐れがないか?という視点での分析です。
事業を営んでいると、モノやサービスを売り買いした際、現金の受け取り・支払いに時間がかかる場合があります。
取引の都度、現金でやり取りすることは稀で、ほとんどの場合が一定のタイミングでまとめてお金を受け渡しします。
この時、相手先がきちんと期限までにお金を支払ってくれるか?という点と、
相手にお金を支払うことが出来るか?という点が重要となります。
要するに、資金がうまく回るかどうかが安全性を判断する際のポイントです。
多くの企業は金融機関からの借り入れがあります。
ただし、借り入れ(借金)があるから危険という訳ではありません。
資金が循環してさえいれば、事業が継続的かつ持久力を持って動いていることになるため、問題はありません。
恐いのは、資金の流れが止まってしまうことです。
お金が回らなくなると、どれだけ利益が出ていたとしても倒産してしまいます。
日々の業務が継続して行えるだけの資金がきちんと回っているか?という点が、安全性を見る重要なポイントです。
成長性とは
成長性とは、その言葉どおり企業が成長する見込みがあるかどうかです。
言い換えると、将来性があるか?ということでもあります。
企業は、前提として永続的に事業を行っていくものであり、長く続けていくためには企業努力が不可欠です。
企業の努力は、積み上げられた利益の有効な活用に表れてきます。
設備投資や新商品の研究開発費に投資されていると、その企業は今後ますます発展する可能性があると見ることができます。
売上の伸び率、利益の伸び率も重要なポイントです。
利益をしっかりと生み出し、新たな投資に力を入れている企業は、将来性があり成長していく可能があるといえます。
その他
決算書を見て分かることは、今挙げた3つの視点が主なものです。
更に細かい視点で見ると、経営が効率よく行われているか?という点や、ムダや偏りがないか?という点、どの時点で利益が出るか?という点なども読み解くことができます。
ただ、ここまでの内容になってくると、経営分析という視点になるのでワンランク上の知識が必要です。
決算書の数字は見てすぐに読める部分と、じっくりと分析しなければ見えてこないものとがあります。
決算書が教えてくれることは多くありますが、より深く読み込むためには、決算書の内容を論理的に組み立てる必要があります。
特に先々の数字を追いたい場合は、現状から未来を想像し、矛盾が無いかを検討し、企業を取り巻く環境を見ていかなければなりません。
決算書を読むということは、根拠に基づく想像力も重要です。
自分のスキルとしてどこまでが必要かを判断し、段階的に決算書を読む力を身につけていきましょう。
決算書からは分からないこと

決算書からは分からない事もある
決算書を読めばその企業のことが分かる!!と言いつつ、決算書をどれだけ読み込んでも分からないこともあります。
決算書にあがってくるのは、あくまでも企業活動の結果です。
その結果から実態を読み、未来を想像することはできたとしても、企業内部の様子は決算書からは読み取ることができません。
読み取ることができない主なものとしては、次のものが挙げられます。
- 企業の持つ人的資源
- まだ世に出ていない新商品・新技術
- 得意先
- 経営戦略
- 強み・弱み など

人的資源
人的資源とは、経営資源「ヒト・モノ・カネ・情報」のなかで、ヒトのみを指して用いられる言葉です。
その企業にどれだけ優秀な社員がいるか、社員の層がどのようになっているかは、決算書からは読むことができません。
新商品・新技術
先々売り出す新商品・新技術は、企業がここぞというタイミングで発表するものです。
開発に充てた費用は決算書の中から見ることができたとしても、その商品や技術の完成のタイミングは決算書には出てきません。
特に、システム開発による社内の効率アップなどは、すぐに結果が表れる訳ではなく長い年月をかけて表れてくるため、見えない数字といえます。
得意先
企業には、少なからず取引を継続的に行う得意先があります。
決算書からは、得意先がどこで、どのような割合でそこに関わっているのかを知ることができません。
極端な話、得意先とその他の企業で9対1という偏りがあるかもしれません。
得意先がその企業に与える影響についても、決算書からは読めないことです。
経営戦略
企業の経営戦略は、決算書に表れるどころか、社員すら知らないという場合も多いです。
過去の経営戦略の結果が今の決算書の数字を作っている…とも言えますが、企業は市場の変化に対応するため、日々様々な戦略を練っています。
現在進行形の戦略もあれば、既に失敗したものや実行に移されずに終わる戦略もあるでしょう。
そのような内部での企業の動きは、決算書からは読み取ることができません。
強み・弱み
同業他社と比較する場合は、決算書を並べて見ることでその会社の強み・弱みが見えてくる場合があります。
しかし、根本的になぜそれが強み・弱みとして表れてくるのか?という内部事情については、決算書からは読み取ることができません。
自社しか知り得ない強み・弱みは、少なからずあります。
その他
貸借対照表は、一定時点の財政状態を表すものです。
それは、言い換えると「決算日のみの残高」を表していると言えます。
そのことから、決算日までに残高がゼロとなったものは、その存在を把握することができません。
例えば、社長が会社からお金を借りたとします。
1年の間にいくら借りたとしても、決算日までに全額を返済していれば、それは貸借対照表に載ってきません。
その次の年も、そのまた次の年も、同じように期中でお金を借りては決算日までに返済をする…
決算日時点で残高がゼロであれば、それは記載されないままとなります。
まとめ
決算書を読むことは、企業分析を行うことに繋がります。
数字の並びばかりで「読む」という言葉がしっくりこないかもしれませんが、決算書はポイントさえ掴めば、見て理解して読むことができるようになります。
決算書と向き合う前に、まずは「決算書を読む」とはどういうことかイメージを掴んでおきましょう。