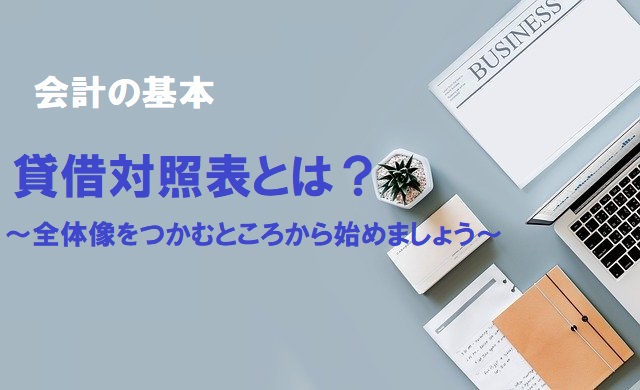こんにちは、 SunnyBizコンサル です。
貸借対照表は、企業の財産状況を判断するうえで重要な資料です。
決算書の中でも主要なものであり、企業の「お金」に関するさまざまな情報を示しています。
ただ、その内容はとても分かりにくく、読み方を知らずに眺めるだけではなかなか情報を得ることができません。
そこで今回は、貸借対照表を読む手がかりとして、そもそも貸借対照表とはどのようなものなのか、その全体像についてまとめます。
ポイントはコチラ。
- 貸借対照表とは
- どんな作りになっているのだろう
- どんなことを表しているのか
- 貸借対照表から分かることとは
まずは、貸借対照表の全体像を知るところから始めてみましょう。

貸借対照表とは?全体像をつかもう

貸借対照表の定義
貸借対照表は、決算書を作成した時点での企業の財産、債務と、返す必要のない元手資金を表す残高の一覧表です。
貸借対照表を見れば、その企業の懐事情が分かります。
一般的に、貸借対照表は「一定時点の会社の財政状態をあらわす」と説明されます。
一定時点とは決算日のことで、例えば4月1日~3月31日の1年間が会計期間であれば、会計期間の最終日である3月31日時点が決算日であり、その時点の残高を表しています。
財政状態を表す貸借対照表
財政状態とは、財産・債務の状況のことをいいます。
貸借対照表がどのように財政状態を表しているか、貸借対象表を見る際のポイントは次のとおりです。
- 貸借対照表の左側を見て資金の使いみちを知る
- 貸借対照表の右側を見て資金をどのように集めたかを知る
貸借対照表に書かれていること
貸借対照表は、真ん中を一本の線で区切ります。
そして、左側には現金・預金、その他の財産など、資金の使いみちが記載されます。
右側には、資金をどのように集めたか、その内容に応じて借入金と元手資金が記載されます。

左側に記載される現金等・その他の財産を総称して「資産」と言います。
右側に記載されるもののうち、いずれ返済する必要のある借入金などの資金を「負債」、返済する必要がない元手資金を「純資産」といいます。


貸借対照表の構成
貸借対照表に記載される資産、負債、純資産は、それぞれ「資産の部」「負債の部」「純資産の部」と区切られます。

貸借対照表はこの図の通り、左側に表される資産の部と、右側に表される負債の部、純資産の部の3ブロックで構成されています。
貸借対照表があらわすもの
見た目は若々しい人であっても、健康診断の結果が悪い…ということがあるように、その企業が大きく見栄えが良かったとしても、経営の実態が良いとは限りません。
貸借対照表は、決算日時点での会社の財産、債務などを表すため、会社の中の状態を知ることができます。
見かけでは分からない企業の中身を表すため、企業の健康状態を表しているといえます。
貸借対照表を構成する3つのブロック

資産の部
資産の部には、会社が持つ現金や商品、土地、建物などが表示されます。
ここには、企業が集めた資金をどのように使ったか?という使いみちが表されています。
現金のまま持っていることもあれば、商品や建物などに形を変えている場合もあるでしょう。
この資金の使いみちは、利益を生み出すための運用であるため、資産の部は「資金の運用形態」という言い方をします。
負債の部
負債の部には、銀行から借りたお金や、仕入先などにこれから払うべき代金などが表示されます。
企業が返済の義務を負うものや、将来にわたって支払うべきものが載ってきます。
自分のものにはならない資金であるため「他人資本」という言い方をします。
純資産の部
純資産の部とは、返還する必要のない資金であり、自己資金や株主からの出資金、過去から今まで積み上げてきた利益が載ってきます。
また、資産にも負債にも当てはまらないものも、ここに入ってきます。
原則として返済の義務がないことから「自己資本」という言い方をします。

「調達」とは、会社がどうやって必要なお金を集めたか?ということであり、その内容ごとに負債の部と純資産の部へ区分して表示します。
資産・負債・純資産の関係
貸借対照表の右と左は必ず一致します。
集めてきたお金は、必ずなにかしらの形で会社が保有(運用)しているため、集めたお金のトータルは資産に載ってくるはずです。
調達源泉である負債・純資産は、運用形態である資産と表裏一体の関係にあります。
資産 = 負債 + 純資産

貸借対照表は、左右が一致するという特徴から「バランス・シート(Balance Sheet)」、頭文字をとってB/S(ビーエス)といわれます。
貸借対照表から分かること

お金の情報
貸借対照表は、お金の動きを表します。
資産の中には、お金そのものである現金・預金と、将来お金として入ってくるもの、売ったらお金になるものがそれぞれ項目ごとに載ってきます。
負債には、将来返すべき出て行くお金が項目ごとに載り、純資産には返さなくても良いお金が載ります。
お金の使い方と集め方が載っているため、企業にとって最も大切といえる「お金」の情報を表しています。
事業の特徴
貸借対照表を見ると、その企業の特徴をとらえることができます。
見るべきところは、資産に載ってくる内容です。
例えば、スーパーなど小売業は、モノを売った時に現金で支払いを受けることが多くあります。
近年キャッシュレスが進んでいるものの、未だに現金のみを使うお店も多くあります。
この場合はモノと同時にお金が動くため、ツケとなるあとから受け取るお金(売掛金)の残高が少ないことが特徴になります。
一方、会社同士で取引する場合や、金額が大きなモノを売買する業種は、現金取引は少なくなります。
現金よりも、売掛金の残高が大きくなる場合が多いでしょう。
このように、貸借対照表の内訳から、その企業の特徴をみることができます。
企業の安全性
貸借対照表は、倒産の恐れがないか?という視点での分析を行うことができます。
企業は、お金が回らなくなると、どれだけ利益が出ていたとしても経営が成り立ちません。
金融機関からの借り入れが返済できない場合や、取引先に仕入れ代金が支払えない…ということが起こると、企業は倒産してしまいます。
倒産の恐れがあるかどうかは、負債と純資産の割合で見る事ができます。
返済する必要のない純資産が大きければ大きい程、必要なお金を自社でまかなっていることになるため、安全な会社であるといえます。
逆に負債の方が大きいと、返済すべきお金に追われることになります。
ただし、企業を経営していくうえでは、金融機関からの借り入れや代金の後払いは必要不可欠といえます。
借り入れがあったとしても、資金がしっかりと回っていれば大きな問題とはなりません。
資金が止まらずに回り続けることと、負債と純資産のバランスが重要です。
企業の安全性を知るひとつのツールとして、貸借対照表を活用できます。
まとめ
企業のことを知ろう!と思った際は、決算書を見ることが先決です。
その中でも貸借対照表は、企業の持つお金に関する情報を明確に示しています。
貸借対照表を実際に「読む」ときに、抵抗感を持たずスムーズに取り掛かれるよう、全体像を把握しておきましょう。