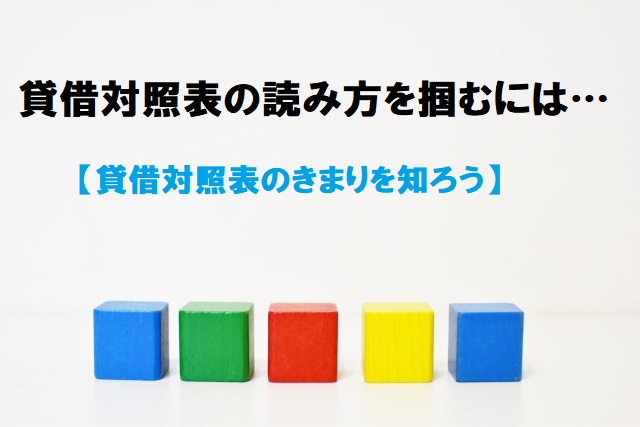こんにちは、 SunnyBizコンサル です。
企業が作成する財務諸表は、経営者だけでなく投資家や金融機関などの外部利害関係者にとっても重要な資料です。
財務諸表は、誰が見ても誤解なく、分かりやすくあるために、きまりに従う必要があります。
そのきまりを理解することは、財務諸表を読む際のポイントを知ることにもなります。
今回は、貸借対照表を読むにあたって読み方のコツを掴むため、貸借対照表のきまりについて解説します。
ポイントはコチラ。
- 貸借対照表にあるきまりごととは
- 貸借対照表のきまりを知ると、貸借対照表を読むポイントが見えてくる?!
- 貸借対照表はどういう視点で見ればいいの?
このきまりを知ることで、貸借対照表を読み解く際の重要なポイントが見えてきます。

貸借対照表を知る

概要
貸借対照表には、「貸借対照表原則」という一定の基準があります。
貸借対照表原則は、項目ごとの並べ方や、表示、区分などを説明しており、企業は、基本的にこのきまりに従って貸借対照表を作成しています。
貸借対照表原則に従うことで、貸借対照表は企業の状態を客観的に表すものとなり、誰が見ても誤解なく分かりやすいものとなります。
貸借対照表の構成
貸借対照表は、企業が決算書を作成した時点での財産、債務と、返す必要のない元手資金を表しています。
貸借対照表を見れば、その企業の懐事情が分かります。
貸借対照表は、真ん中を一本の線で区切ります。
そして、左側には現金・預金、その他の財産など、資金の使いみちを、
右側には、資金をどのように集めたか、その内容に応じて借入金と元手資金が記載されます。

左側に記載される現金等・その他の財産を総称して「資産」と言います。
右側に記載されるもののうち、いずれ返済する必要のある借入金などの資金を「負債」、返済する必要がない元手資金を「純資産」といいます。
この記載自体も、貸借対照表原則に従ったものです。
貸借対照表に記載される資産、負債、純資産は、それぞれ「資産の部」「負債の部」「純資産の部」と区切られます。

貸借対照表はこの図の通り、左側に表される資産の部と、右側に表される負債の部、純資産の部の3ブロックで構成されています。
貸借対照表のきまりごと
貸借対照表が企業の情報を正しく表すためには、さまざまなきまりに従う必要があります。
主なものは、以下の通りです。
- 勘定科目ごとにまとめて記載
- 資産と負債はさらに二つに区分する
- 総額で表示する
- 貸借対照表は表の左右が一致する
それぞれ、次の章で詳しく見ていきます。
貸借対照表のきまりごと

勘定科目ごとにまとめて記載
企業が持つ財産・債務にはさまざまなものがあります。
これらを、そのモノごとにひとつひとつ記載することは実務的に不可能です。
現金、債権、商品、借入金など、類似する取引はその内容ごとにまとめて記載することになっています。
そのまとめる項目・分類を「勘定科目」と言います。
貸借対照表に記載される資産、負債、純資産は、勘定科目ごとに合計金額で並べて表示します。
資産と負債は二つに区分する
勘定科目で分類されたものは、その内容ごとにそれぞれ資産の部、負債の部、純資産の部に振り分けられます。
この時、資産の部・負債の部については、その中で「流動」と「固定」の2つに区分されます。

流動資産とは、現金そのものや1年以内に現金化される資産のことです。
流動負債とは、1年以内に支払期限がくる借金などのことです。
流動資産についての記事はコチラ↓↓↓
固定資産とは、1年を超えて長期にわたって保有するものや、現金化するのに1年超の時間が必要となる資産のことです。
固定負債は、支払期限が1年を超える借金などのことです。
固定資産に関する記事はコチラ↓↓↓

また、正常な営業取引から発生する掛け取引(売掛金)や、手形取引(受取手形)、商品についても、毎月のように発生・回収を繰り返すため、流動性が高いと見ることができ「流動資産」に分類されます。
負債についても、正常な営業活動から発生する掛け取引(買掛金)や、手形取引(支払手形)は、流動性が高いため「流動負債」に分類されます。

総額で表示する
資産・負債・純資産は、総額によって表示しなければならないというきまりがあります。
これを、総額主義の原則と言います。
企業によっては、同じ取引先で売ったり買ったりすることがあると思います。
その際、売った金額と買った金額を相殺することなくそれぞれ総額による表示を求めているのが、総額主義の原則です。
億単位の取引があったにもかかわらず、相殺された残高でどちらか一方しか表示されていないと、取引規模や財政規模を把握することができません。
資金の運用形態と調達源泉をしっかりと明示するため、総額主義は重要です。
貸借対照表は表の左右が一致する
貸借対照表の右と左は必ず一致します。
集めてきたお金は、必ずなにかしらの形で会社が保有(運用)しているため、集めたお金のトータルは資産に載ってくるはずです。
調達源泉である負債・純資産は、運用形態である資産と表裏一体の関係にあります。
資産 = 負債 + 純資産

貸借対照表は、左右が一致するという特徴から「バランス・シート(Balance Sheet)」、頭文字をとってB/S(ビーエス)といわれます。
きまりがあることで分かること

資金繰りを知ることができる
貸借対照表の資産の一番最初にくるのは「現金・預金」です。
現金・預金は、流動的で換金性に優れており、必要な時にすぐに支払いに回すことができます。
また、正常な営業取引から発生している掛け取引(売掛金)や、手形取引(受取手形)についても、毎月のように発生・回収を繰り返すため、流動性が高い資産と言えます。
この流動性が高い資産(流動資産)は、流動性の高い負債(流動負債)と比較することで、資金繰りを見ることができます。
流動資産の額が、流動負債を上回っている時は、支払い能力に問題なしと判断できます。
逆に、流動資産よりも流動負債が多い時は、資金がまかなえていないと言えます。
その状況が続くと資金繰りが深刻化し、支払いに苦労することになります。
最悪の場合、資金を回すことができず、倒産へと向かう可能性があります。
貸借対照表は、一定のきまり(基準)で科目を振り分けるため、その割合や比率から資金繰りについて検討しやすいといえます。
現金化のタイミングを知ることができる
決算書を読む際、「現金化のタイミング」を知ることは企業の安全性を判断するうえで重要です。
資産、負債を「流動」と「固定」に分類する――。
これは、現金化のタイミングを見ることを意味しています。
企業にとって、現金は血液ともいえる重要な財産です。
血液がドロドロになり流れが悪くなると命が危険であるように、現金が回らなくなった時、企業はとても危険な状態になります。
どれだけ利益が出ていても、動かせるお金がなければ倒産してしまいます。
企業が持つ財産・債務は、どんな姿のものであっても、もとは現金です。
貸借対照表の「流動」「固定」を読み取ることは、そのモノから現金化のタイミングを知ることができるため、これからどのようにお金が回っていくかを把握し、予測することができます。
視覚的に捉えることができる
貸借対照表は、ひとつひとつの項目を数字で見なくても、区分ごとにブロックとして視覚的に見ることができます。
下の図のように、流動資産、固定資産、流動負債、固定負債、純資産というように、全体を5つのブロックで視覚的に捉えることができます。

数字が読めなくても、図として把握することができれば、それぞれの割合を大まかに把握することができます。
そして、その割合が企業にとって安全かどうか?を分析することで、大まかではあるものの企業の安全性を把握することができます。
まとめ
貸借対照表を何も知らずに眺めると、何をどう読んでいいか分からず、的確な情報を得ることはできません。
内容を把握するためには、貸借対照表がどのような作りになっているかを知る必要があります。
貸借対照表のきまりを知り、貸借対照表を読み解くことへ繋げていきましょう。