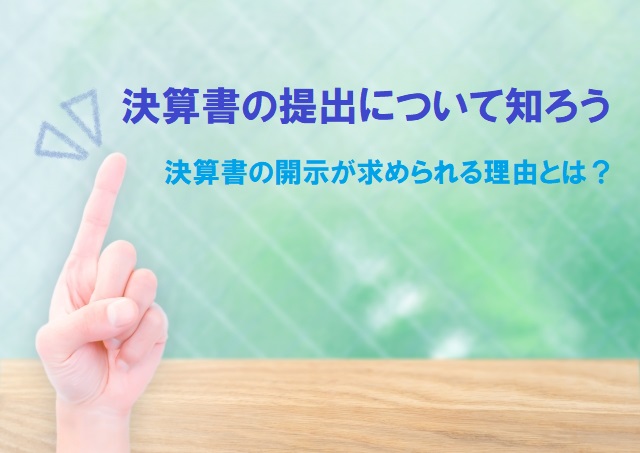こんにちは、 SunnyBizコンサル です。
決算書の作成は、事業を営むすべての法人に義務づけられています。
1年間の事業活動を記録し、決算を行い、決算書を作成するという一連の流れは、事業の規模に関わらず必須の業務です。
作成した決算書は、提出を求められることがあります。
決算書を提出・公表することを「開示」と言います。
では、どのような場面で開示が必要となるのでしょうか?
今回は、関係先ごとに決算書がどのように活用されるかを確認し、決算書の開示が求められる理由について解説していきます。
要点はコチラ。
- 決算書の作成目的は自社のためだけじゃない?!
- 決算書の開示先は?
- 決算書はどのように活用されているの?

決算書の開示が求められる理由

決算書の作成目的
1年間にどのような取引があったのか?どんなお金の動きがあったのか?を集計し、とりまとめる作業を決算と言います。
企業は、決算でとりまとめた情報を「決算書」という書類一式で表します。
決算書は企業の事業活動を集約した重要な資料であり、企業の成績表ともいわれます。
決算書を作成する目的は、企業の実情をまとめることと、それを関係先へ開示するためです。
決算書の作成は、会社が業績を知るためだけのものではなく、外部への開示が目的のひとつであることを知っておきましょう。
決算書の開示が求められる理由
決算書のうち、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の3つを読めば、その企業の実情をほぼ把握することができます。

外から見ると大きく儲かっているように見える企業であっても、しっかりと内部を見ないとその実態を把握することはできません。
決算書を読むことで、しっかりと儲かっているか?倒産の恐れがないか?今後も成長していくのか?といった企業状況を見ることができます。
あらゆる情報が詰まった決算書は、外部に居ながらでも企業の実情を把握できる情報ツールであるため、様々な関係先にとって必要不可欠なものです。
その企業のことを知るために、関係者は開示を求めることとなります。
決算書の開示は、義務として必ず開示しなければならない相手先と、任意の相手先があります。
決算書を開示する相手先

決算書は、開示義務に従って開示する場合と、任意の請求に応じて開示する場合とがあります。
決算書の開示義務
決算書を開示しなければならない場合は、次のとおりです。
- 税務署へ申告するとき
- 上場企業・大企業の一般開示
- 特定の株主から求められたとき
- 債権者から求められたとき
税務署
税務署は、決算の内容に不備・不正が無いかを確認します。
そのため、決算書は税務申告資料と一緒に必ず提出しなければなりません。
上場企業・大企業の一般開示
上場企業は、決算書を開示しなければなりません。これは金融商品取引法に定められています。
また、上場はしていなくても「大企業」と言われる企業は、決算書の開示が義務付けられています。
特定の株主
株主は会社の所有者であるため、持っている株の割合(持分比率)によっては、決算書の開示を求めることができます。
会社法(433条)は、3%以上の株式を保有している株主は、閲覧を請求できるとしています。
債権者
債権者は、債権の回収がきちんとできるかどうかを知るため、決算書の開示を請求することができます(会社法442条)。
決算書の任意開示
次に掲げる場合は、任意の開示となります。
- 金融機関から求められた場合
- 取引先から求められた場合
- その他(社員・関係者など)
これらはあくまでも任意であるため、経営者の判断で開示をするか否か決めましょう。
ただし、金融機関や主要な取引先は、会社が安全な状態であるかを知ったうえで取引を望む場合があるため、本来は開示義務が無くても決算書開示を強く要求される場合があります。


決算書の活用について

決算書の活用は関係先によって様々です。
決算書がどのように活用されていくのかを見ていきましょう。
経営者の指標
決算書は、業績把握のため、意思決定のため、経営分析のため、経営者にとって最も重要な資料といえるでしょう。
経営者は常に自社の状況を把握しておかなければなりません。
長く永続的に企業を盛り上げていくためには、現状分析から未来へ繋げていくため決算書の読解が必要不可欠です。
自社をしっかりと把握するには、ただ決算書の数字を見るだけでなく、数字を細かく分析する必要があります。
日々の取引や決算書の数字を基礎に、より経営の実態が分かるよう数字を分類したり、加工を行う会計として、管理会計があります。
管理会計は、社内で活用するための会計であり、利益率の把握や、コスト管理、予算管理ができるため、経営戦略に大いに役立ちます。
現状の見直しや、未来へ向けた経営判断に役立てるためのものとして、決算書は経営者の指標として活用されます。
税務署への申告資料
すべての企業は税務署に決算報告書を開示しなければなりません。
税務署は、決算書と税務申告資料を見て取引や税金の計算に不備・不正が無いかを判断します。
税金を減らすために、売上を少なく見積もっていないか、経費を多く計上していないかなど、不当な利益操作が無いかを確認します。
また、会社のお金が経営者など役員に私的に流用されていないか、不正資金の動きも確認しています。

投資家への報告資料
投資家(株主)は、企業が発行する株を売買することで、株価の変動による利益を得ます。
企業の業績が良かったり成長性が見込める場合は、株価は上向きになる傾向があるため、企業の実情判断に決算書が不可欠です。
また、企業が利益を多く出せば、投資家はより高いリターン(配当)を得る可能性があるため、企業がきちん利益を出しているか、利益を出す見込みがあるかを判断します。
投資家は、企業の収益性(利益を生み出す力)を重視するため、決算書の中でも損益計算書を重視して活用しています。
債権者への開示資料
債権者の主なものとして、金融機関が挙げられます。
金融機関は、融資を行う際、貸し出したお金がきちんと回収できるか返済能力の有無を判断します。
また、その企業の成長性を判断するうえでも決算書を活用します。
決算書を見て先々成長が見込めると判断できる場合は、現状が赤字であったとしても、融資を実行し、成長を後押ししてくれます。
金融機関などの債権者は、企業の返済能力や成長性を判断するため、決算書の中でも貸借対照表を重視して活用します。
その他関係者
その他の関係者としては、取引先や従業員などその企業に関わる者が挙げられます。
取引先は、主に商品やサービスを提供した時、相手がその代金を支払うことができるか?という支払い能力について判断します。
決算書を見て取引先の経営状況が危ういと思えば、より安全に資金を回収するため支払期限を短縮したり、取引の縮小などを行うでしょう。
逆に、業績が好調で大口の取引ができると判断できれば、取引の拡大や価格交渉を行ってくる場合もあります。
従業員にとっても、決算書は自社の業績を知る重要なツールです。
上場企業や大企業でない限り、いち個人が決算書を見ることはなかなか無いかもしれませんが、業績を知るには決算書を見るのが一番手っ取り早いです。
決算書を見ることが出来ない場合は、自分自身の給与やボーナスが例年に比べてどうだったか?という事もひとつの判断基準となります。
その他の関係者は、相手先の状況はどうかな?うちの会社は大丈夫かな?というような、信用調査を名目として決算書を見る場合が多いといえます。
まとめ
決算書は、その企業の実情を表す重要な資料です。
自社だけで内容を把握し活用するのではなく、時に、求めに応じて情報を開示する必要があります。
決算書の活用方法は開示先ごとに異なるものの、必要な情報を適切に開示することは、企業として必要な責任といえるでしょう。