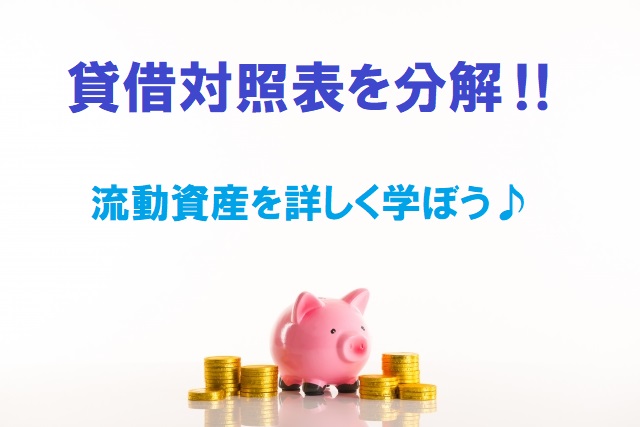こんにちは、 SunnyBizコンサル です。
貸借対照表は、企業の経営状況を判断するうえで重要な資料です。
決算書の中でも主要なものであり、企業の「お金」に関するさまざまな情報を示しています。
貸借対照表にはたくさんの情報があります。
ただ、その情報を正しく読み取るには、どこに何がどのように記載されているかを知る必要があります。
今回は、その点を見ていくため、貸借対照表を分解し、資産の部にある「流動資産」に着目して解説します。
ポイントはコチラ。
- 貸借対照表の構成を知る
- 流動資産とはどういうものなの?
- 流動資産の中身は分解できる?!
- 流動資産を知ることで分かることとは?
貸借対照表を分解し、個別に見ていくことで、貸借対照表を読む際の視点が身についてきます。
貸借対照表を読む際の基礎知識として、流動資産の理解を深めましょう。
貸借対照表の構成

概要
貸借対照表は、企業が決算書を作成した時点での財産、債務と、返す必要のない元手資金を表しています。
左側には現金・預金、その他の財産など資金の使いみち、
右側には、資金をどのように集めたか、その内容によって借入金と元手資金が記載されます。

貸借対照表を見れば、その企業の懐事情が分かります。
貸借対照表の構成
左側に記載される現金等・その他の財産を総称して「資産」と言います。
右側に記載されるもののうち、いずれ返済する必要のある借入金などの資金を「負債」、返済する必要がない元手資金を「純資産」といいます。
貸借対照表に記載される資産、負債、純資産は、それぞれ「資産の部」「負債の部」「純資産の部」と区切られます。

貸借対照表はこの図の通り、左側に表される資産の部と、右側に表される負債の部、純資産の部の3ブロックで構成されています。
資産の部の構成
貸借対照表の左側にある資産の部は、その中で「流動資産」と「固定資産」の2つに区分されます。

流動資産とは、現金そのものや1年以内に現金化される資産のことです。
固定資産とは、1年を超えて長期にわたって保有するものや、現金化するのに1年超の時間が必要となる資産のことです。
このように、決算日の翌日から1年以内に現金化されるかどうか?という基準で区分することを「1年基準(ワンイヤー・ルール)」と言います。
また、正常な営業取引から発生する掛け取引(売掛金)や、手形取引(受取手形)、商品についても、毎月のように発生・回収を繰り返すため、流動性が高いと見ることができ「流動資産」に分類されます。

今回見ていくのは、赤枠で囲った「流動資産」の部分です。
流動資産について知る

流動資産の特徴
流動資産は、その文字通り流動性がある資産です。
流動性があるとは、すぐに現金化できることを意味しています。
現金そのものや1年以内に現金化される資産であり、お金になりやすいか?という視点で固定資産と区分して表示します。

流動資産に載る主なもの
流動資産に載る主なものとして、以下のものが挙げられます。
- 現金
- 預金
- 受取手形
- 売掛金
- 有価証券
- 商品(製品)
- 原材料
- 未収金
- 前払費用
- 短期貸付金
- その他
- 貸倒引当金(マイナス表記)
現金・預金
現金・預金はお金そのものです。
預金には普通預金、当座預金、定期預金などがあります。
受取手形
受取手形は受け取った手形のことであり、期限が来れば手形に記載されている金額を受け取ることができます。
また、期限より前であったとしても、手形を金融機関へ提示すれば現金に換えることができます。
この場合は、期日前の換金ということで当初の金額から割引された額を受け取ることになります。
売掛金
売掛金は、商品を販売したものの商品代金がツケの状態でまだ受け取れていないものです。
取引先に支払期限を提示し、約束の期日までに入金をしてもらいます。
有価証券
株式などを購入した場合「有価証券」として計上します。
有価証券には、売買目的のものと投資目的のものがあります。
流動資産には、短期的に売買を行う予定の有価証券が載ってきます。
商品(製品)・原材料
商品、原材料の在庫は、売ってお金に換えることができるため、流動資産に載ります。
そのほかにも、業種によっては「仕掛品」という、製造途中の未完成品が表示されることもあります。
未収金
有価証券や固定資産の売却代金など、本業以外の取引から発生した未回収の金額を表します。
通常の営業から発生する売掛金とは区別されるものであり、売掛金以外の未回収金額です。
前払費用
前払費用は、次の期(翌期)に発生する費用の先払い分です。
家賃や保険料は、実際の利用よりも先に払うことが一般的です。
これは権利を買っている状態であり、前払費用は翌期にサービスを受けられる権利のことを意味します。
短期貸付金
短期貸付金とは、仕入先や取引先、従業員・会社役員などに貸し付けたお金であり、1年以内に返済されるものです。
決算日を基準として、1年以内に返済があるかどうかによって短期か長期かを判断します。
その他
その他、上記以外のもので商品の手付金などを表す「前払金」や、税金の前払である「繰延税金資産」などもあります。
貸倒引当金(マイナス表記)
貸倒引当金とは、売掛金や受取手形が取引先から万が一回収できなかった場合のリスクを、あらかじめ適切な比率で計算したものです。
売掛金や受取手形は、相手先が倒産すると回収が見込めなくなってしまいます。
いつ起こるか分からないリスクに備え、回収できないと見込まれる金額を資産からマイナスして表示します。
勘定科目の並びに関するルール
貸借対照表に載る勘定科目は、一定のルールに従った並び方をしています。

貸借対照表では、「流動性配列法」というルールに従って勘定科目を並べます。
これは、資産であれば「現金」を一番上として、流動性が高い順に並べる方法です。
流動性が高いということは、換金性が高いことであり、すぐにお金として使えるものから順に並ぶことになります。
流動性が高いかどうか?という判断をするには、その勘定科目がどういった性質であるかを知る必要があります。
貸借対照表を読み解くためには、それぞれの勘定科目を理解することも重要です。

流動資産の分類

流動資産は3つに分類できる
流動資産に載ってくる勘定科目は多くあります。
流動資産は、現金化しいやすい順番に以下の3つに分類することができます。
- 当座資産
- 棚卸資産
- その他の資産
以下、それぞれに見ていきます。
当座資産
当座資産とは、現金と短期間で現金化することができる資産のことです。
具体的には、預金・売掛金・受取手形・有価証券などが挙げられます。
これらは換金性が高く、資金繰りに影響するものであるため、企業の支払い能力を表すものです。
流動資産の中でも当座資産がうるおっていると、すぐに支払いに回せる資金があると見ることができるため、その企業は安全性が高いといえます。
貸借対照表を読み解く視点として、当座資産と流動負債を比較することを意識してみましょう。
流動負債を十分にまかなうだけの当座資産があれば、支払い能力はまず問題ないとみることができます。
棚卸資産
棚卸資産とは、商品・製品・仕掛品など、在庫のことを意味します。
棚卸資産は、売ればお金に変わるものの、売れたとしもすぐに現金とはならず、「売掛金」としてプールされる場合がほとんどです。
支払いの期日がくるまで待たなければ手許現金にはなりません。
棚卸資産は売上によって定期的にお金を生み出すものであることから、流動資産に記載されます。
ただ、当座資産に比べると流動性が低く換金性が低いものといえます。
ここでひとつ、棚卸資産を見るときのポイントです。
棚卸資産は多すぎても少なすぎても良くありません。
多すぎる場合は在庫として抱えすぎている可能性があり、時代遅れのものや、価値が下がったもの、いつのものか分からないような不良品が混在している場合があります。
在庫が多すぎると倉庫代など管理費用がかかったり、廃棄処分という損失になる可能性もあります。
棚卸資産が多い=資産価値が高い!とは一概には言えないため、注意しましょう。

その他の資産
当座資産、棚卸資産に属さないものが、その他の資産です。
先ほど「流動資産の内容」で挙げた未収金・前払費用・短期貸付金などがそれにあたります。
その他の資産は、それぞれにタイミングこないと現金化することができないようなものです。
例えば、短期貸付金。
これは、取引先からの返済日がこないと現金化できないものです。
資産として持っていたからといってこちら都合で換金できないため、換金性が低いです。
また、サービスを受ける権利である前払費用は、現金化されるものではなく、価値として存在するものです。
これらのことから、その他の資産は流動資産の中でも下の方に記載されます。
まとめ
貸借対照表の資産の部、流動資産について詳述してきました。
流動資産を読むポイントはひとつ、現金化しやすいか?という視点です。
現金化しやすい資産をどの位持つかによって、支払い能力を判断することができます。
貸借対照表を読む際は資産の部の流動資産に着目し、支払い能力の有無を判断してみるといいでしょう。