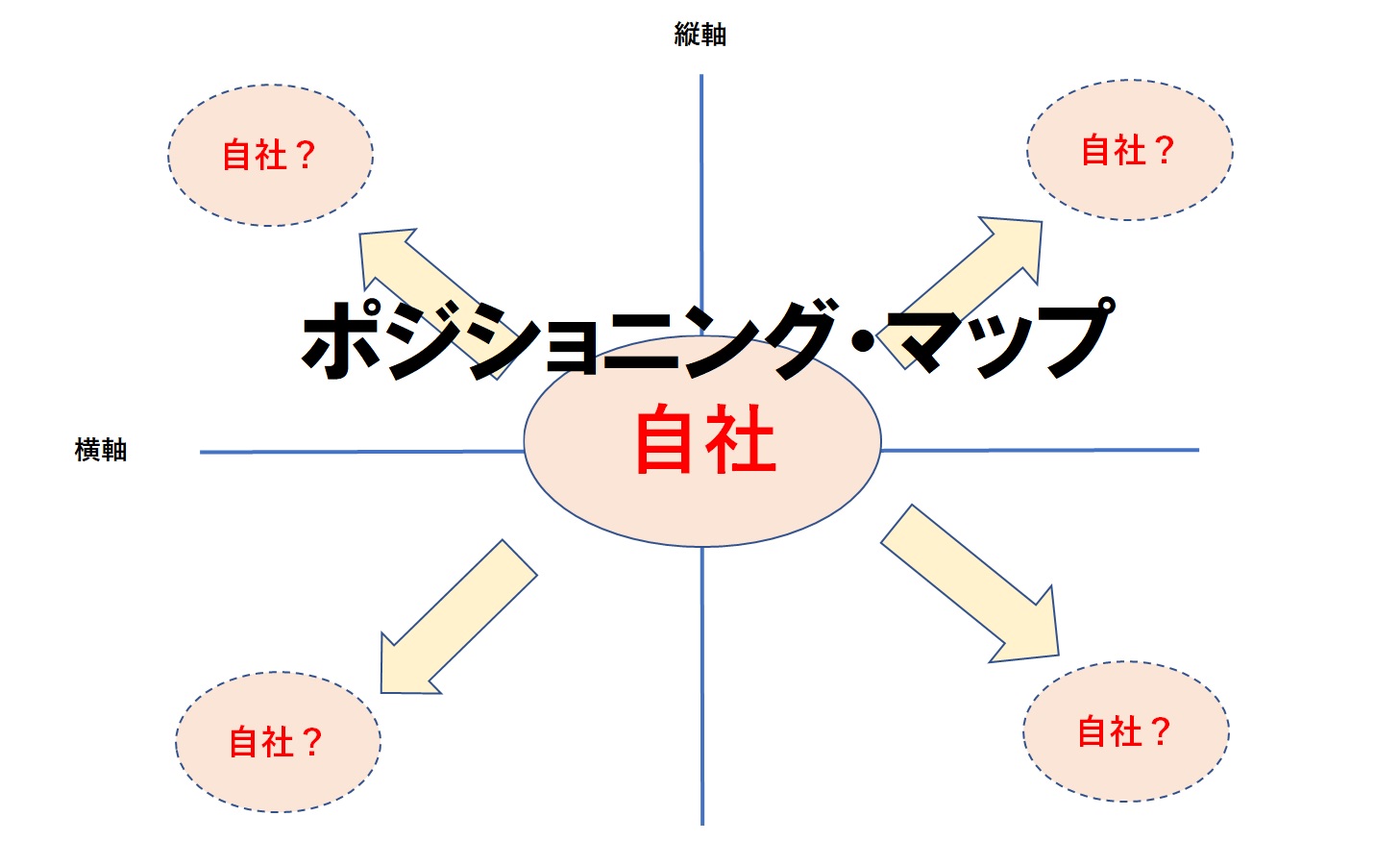こんにちは、SunnyBizコンサル です。
今回は、販売戦略を立てる際に『戦わずして勝てる』空白のマーケットをみつけだす、ポジショニング・マップについて解説します。
自社が顧客に選ばれる存在になれたら・・・
他社との競争がない領域で利益をあげることができたら・・・
それはだれもが理想と考える状態ですよね。
ポジショニング・マップは、この2つを理想ではなく現実的に捉えるために行うフレームワークです。
この記事では、ポジショニング・マップについての理解を深めるため、概要から実際の手順についての説明を行っています。
活用するうえでの注意点についても触れているので、手順と注意点を確認しながら取り組んでみて下さい。

ポジショニング・マップとは?

ポジショニング・マップとは?
市場で競争優位な立ち位置をとり、他社と競争の無い独占的な領域が見つけられたら…
これは誰もが理想に思うことですよね。
他社との競争が無く、顧客に選ばれる位置にいられることは、企業として最高の強みです。
その唯一無二の立ち位置を見つける際に活用するフレームワークを、ポジショニング・マップといいます。
ポジショニング・マップは、競争が激しいマーケットの中で、自社が優位な立ち位置をとるために活用するものです。
ポジショニングの確認
まず、企業が販売活動を行う際には、市場における自社の立ち位置を把握しておくことが重要です。
それを、マーケティングではポジショニングといいます。
ポジショニングは、競合他社との比較や業界での位置づけではなく、顧客の中でどういう風に認識されるかという、顧客の中での自社の位置づけを表します。
「〇〇といえば?」と聞かれて「△△!」と出てくる企業は、顧客の中にポジショニングが出来ているといえます。
ポジショニング・マップは、そのポジショニングを考えるうえで活用するものです。
ポジショニング・マップを活用する目的
ポジショニング・マップを活用する目的は2つあります。
- 市場において自社がどこに位置するか、客観的に知るため
- これから市場で、どのポジションに位置するかを決めるため
①については、既に市場に参入している場合に、他社と比較して自社がどの位置にいるかを客観的に見るために活用するものです。
競合他社との比較、もしくは他社の製品と自社の製品を客観的に比較して、改めて自社の立ち位置を把握します。
そして、このままのポジションでいくのか、ポジションを変える戦略を考えるのか、現状把握と先の戦略の意思決定に役立てます。
②については、他社と差別化ができるポジションを探すことを目的とするものです。
新規参入する場合や新商品を出す場合に、どの領域に商品・サービスを投入するか、その領域を見つけるために活用します。
もしも空白の領域が見つかればそこは成功のチャンスとなるため、その領域を探すことが目的です。
いずれにしても戦わずして勝てる市場の穴場を探すものであり、競争優位な立ち位置をとるために行うフレームワークです。
ポジショニングマップの活用手順

ポジショニングマップを活用する際の手順は、以下の通りです。
縦軸と横軸の設定
まず、顧客が商品やサービスを購入する際に重要視する要因を、縦軸と横軸で組みます。
縦と横に十字を描き、上と下、右と左が相反する事柄になるように、軸の要因を決めます。
その際には、中心に顧客がいると考え、一番中立的な場所から4つの領域にどう顧客が動いているかを見るつもりで取り掛かりましょう。
ポジショニング・マップの軸の取り方
ポジショニングの切り口として、なにを軸に考えるか、その軸の取り方がとても重要です。
軸の要素として取り入れる視点をいくつか例にあげます。
- 価格…高い安い、贅沢かリーズナブルかなど
- 環境…都内か郊外か、住宅街かオフィス街か、大都市か中規模か、都会か田舎かなど
- 価値観…おしゃれかカジュアルか、品質か量か、デザイン性か機能性かなど
- 場面…くつろぐか楽しむか、静かか賑やかかなど
- 時間…短いか長いか、テイクアウトか滞在型かなど
- 人物…若いか年配か、大人か子供かなど
- 容量…多いか少ないか、大きいか小さいか
縦と横2つの軸は、顧客の視点に立ち何を要素に購買の意思決定をするか、その判断となる切り口を考えて組むことが重要です。
軸をとる際は、価格など数値化できるものと、サービス的な要素の数値化できないものを組み合わせると、ターゲットに合ったポジショニングが考えやすいでしょう。
他社と自社のポジションを並べてみる
軸が決まったら、マップ上に他社と自社を配置してみます。
企業そのものの位置として配置するのも良いですし、他社と自社の特定の商品やサービスを配置するのもいいでしょう。
縦軸と横軸の中のどこにそれが位置するのかを並べ、業界の全体像を把握します。
空白のポジションを探す
他社と自社の配置をながめ、他社と差別化できる自社のポジションを探します。
他社が手を出していない領域にポジションを置くことができればビジネスチャンスが広がり、大きな成功につながるでしょう。
ただし、他社が手を出していない領域が、そもそも市場として機能せず空白で残っていることもありえます。
なぜ空いているのか、その原因をよく確認したうえで、空白のポジションを見つけましょう。
ポジショニング・マップの注意点

ここでは、ポジショニング・マップを作るうえでの注意点について説明します。
縦軸と横軸の取り方
ポジショニング・マップを作る時の縦軸と横軸は、類似した要因にならないように注意が必要です。
例えば縦軸を「価格」、横軸を「機能性」で選んだとします。
価格が高ければ機能性が高く、価格が低ければ機能性が低いというのが一般的です。
品質においても同じことが言えるでしょう。
そのため、類似する要因で二つの軸を取った場合には、下の図のように斜め一直線に並ぶような配置になってしまいます。

これでは有効なポジショニング・マップとはいえません。
自社のポジションを明確にするには、できるだけ2つの軸に関連性がないものを選ぶ必要があります。
顧客の視点
ポジショニングを決める際は、顧客の視点で客観的に考える必要があります。
顧客を真ん中に置いて考えた場合、どこにいる企業が必要とされやすいのか、顧客のニーズがどこに向いているかを見極めてポジションを検討する必要があります。

他社がいない事で「空いている!」と思った場所があったとしても、そこにニーズが存在しなければ、そこに入る意味がありません。
他社との比較を考えるあまり、顧客ニーズから離れ独自路線に進むこともあり得るので、あくまでも顧客ありきで考えるということを忘れないように注意しましょう。
ポジショニングは顧客視点で、顧客のイメージの中に作られるものであることを今一度確認して下さい。
顧客への到達可能性を確認
ポジショニングマップの活用により、空白地帯をみつけることができたら、そこに辿り着く可能性と道筋を必ず確認する必要があります。
せっかく空白地帯をみつけたとしても、その位置に到達し、利益をあげることができなければ意味がありません。
例えば、その空白の地帯に商品・サービスを投入する際の広告戦略が明確に見えるか。
市場の規模、売上見込み、利益目標がおおよそ計算できるか。
コストの回収が短期間で見込めるか、もしくは、コストを上回る利益の確実性があるか。
そして、顧客ニーズを満たすことができるか。
道筋を考えた際、もしも到達までの道が見えなければ、それは顧客ニーズが無いか、他社があえて入らなかった魅力のないポジションである可能性があります。
空白地帯はブルーオーシャンとなり得ますが、そこにしっかりとニーズがあるかどうかを分析することも重要です。
なぜ空白なのか?その要因をしっかりと考える必要があります。
重複している領域を見る
重複している領域は、競争が激しいということを表しています。
その重複している領域は、あえて参入する必要がない場所であり、捨てるべきマーケットです。
空白の領域だけを見るのでなく、捨てるべきマーケットについてもしっかり見るようにしましょう。
そうすれば、何が要因で重複しているのか?ということを分析でき、他社と差別化できる部分をみつけることに繋がります。
具体例:カフェ業界のポジショニングマップ

外食カフェ業界についての、ポジショニングマップを作ってみました。
価格による縦軸と、シチュエーションによる横軸で、現在の市場に存在するカフェ店を配置します。
すると、右下の緑色で囲んだ部分が、ぽっかりと空いていることが分かります。
低価格でオフィシャルなお店を考えた際、ここは他社が参入していない空白の市場であることが分かります。
その領域にニーズがあり、ビジネスチャンスになるということであれば、ここを他社と差別化できるポジションとして、商品・サービスを投入します。
逆に、お店が重なる場合や隣接する場合には、競争が激しいことを意味します。
2つの軸で他社と自社を配置してみることで、視覚的に市場を捉えることができます。
まとめ
マーケットの穴場は「ブルーオーシャン」という言葉で表現され、競争がないきれいな海を意味します。
自社の持つひとつひとつの商品・サービスで空白地帯を探してみると、10のうち9は競争必須であっても、残りの1の部分で競争なくして勝てる領域があるかもしれません。
その1つが顧客の中でのポジショニングになると、その領域は独占状態になります。
その1つが、9の商品・サービスよりも大きな売上・利益を生み出すことに繋がります。
戦わずして勝てる穴場を見つける手段として、ポジショニング・マップを活用しましょう。