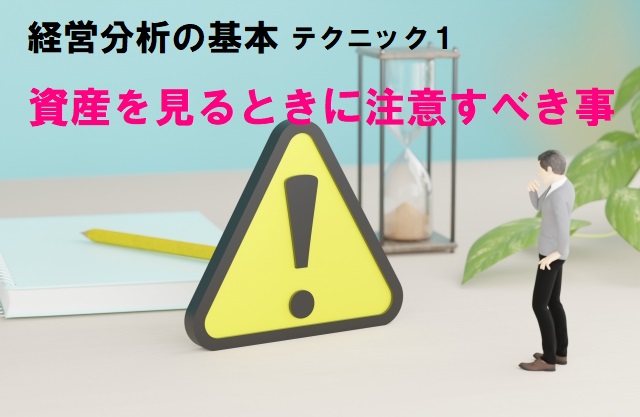こんにちは、 SunnyBizコンサル です。
名ばかりの資産に注意!!
注意喚起からのスタートです。
今回は、経営分析の基本として、貸借対照表を分析する上での注意事項に触れます。
貸借対照表は、会社の財政状態を表します。
言ってみれば、会社にとっての価値ある財産と負うべき債務の一覧表です。
それを見れば、その会社にどれだけの資産と負債があるか客観的な数字を知る事ができます。
貸借対照表の概要についておさらいしたい方はコチラの記事をご覧ください↓↓↓
ただ…
その数字を正しく読むことができていますか?
表面上の数字だけを見ていませんか?
資産には会社にとって価値があるもの、いわば財産が羅列していますが、本当にそれは財産として価値があるものでしょうか。
経営分析をする際の着眼点として、貸借対照表を見るときに注意すべき事を解説していきます。
貸借対照表を疑ってみましょう
探ってみましょう
深読みしてみましょう

経営分析の基本:現金・預金の出所を探れ

そのお金どこから来たの?
貸借対象表の一番最初にくる、現金及び預金。
会社によっては、億を超える数字が並びます。
現金預金の桁数が多いと、
- この会社はお金を持っている
- 資金繰りがいい
- 支払い能力が高い
と判断しがちです。
ちょっと待った!!
現金預金の残高を見て、本当にお金があると判断できますか?
資金繰りが良いといえるでしょうか。
ここで重要なのは、その資金がどこから来たのか、ということです。
実績を伴った資金であるかどうか
現金預金の残高が、売上によって増加し資金が潤っているのであれば、それは優良企業であり大変望ましい結果といえます。
しかし、現金預金が増える原因は、他にもあります。
□銀行借り入れ
□社長借り入れ
□固定資産や株の売却
□その他の臨時収入
このように、売上ではなくても現金預金が増えることがあるのです。
重要なのは、現金預金の増加要因をしっかりと探り、分析することです。
借り入れによる資金の増加
会社は、しばしば銀行より借り入れを行います。
借りたお金は預金口座に入金されるため、借り入れ額によっては一気に何千万・何億と残高が増加します。
現金・預金の残高の増加が、ほとんど銀行からの借入資金だったら・・・
一時的に資金が潤沢に見えるだけで、それは返済を伴う資金であるため決してお金がある状況とはいえません。
社長が会社にお金を入れた場合も同様です。
会社が生み出した資金でない限り、現金預金の残高がいくら多かったとしても、決して財政状態が良いとはいえないのです。

資産の売却による資金の増加
資金が増加する要因には、固定資産や株の売却も考えられます。
これは、単に現金比率をあげたとみることもできますが、場合によっては企業の財政状態の悪化を表していることもあります。
資金を調達する方法として借り入れが出来なかった場合には、モノをお金に換えて資金を生み出すしかありません。
自社が持つ固定資産(土地や建物)や株を売却することで資金を工面することもありえます。
その場合は、ただ固定資産が現金預金に移っただけです。
ひどい場合には、事業縮小を意味しているのかもしれません。
固定資産に大きな動きがないかを確認しましょう。
また、損益計算書の特別利益・損失の箇所に、固定資産や株の売却損益が発生していないかを確認することも大切です。
その他の収入
臨時的なものとして、補助金・助成金・給付金などの収入もあります。
一定の要件を満たすことで、返済不要の資金を得ることができ、売上があがらずとも資金の増加がみられることがあります。
コロナ禍においては、国や地方自治体から数多くの補助金・助成金が支払われました。
これによって、現金預金が増加した会社も数多くあるでしょう。
ただし、その収入は一過性のものです。
補助金などの臨時収入については、一般的に損益計算書の雑収入に計上されます。
前年に比べ雑収入が多額にのぼる場合には、補助金等の収入があったとみることができるでしょう。
経営分析の基本:商品の価値を疑え

商品の価値はあるのか?
資産の中での代表格が、流動資産に記載される商品や製品。
これらは、本来売れればお金になるものであるため、財産として資産価値があるものです。
しかし、その中には必ずしも売れるとは限らないものも含まれます。
それが滞留在庫(不良在庫)です。
滞留在庫とは?
ひとことで言うと、売れる見込みのない商品のこと。
滞留在庫とは、倉庫に眠ったままの商品であり、値下げなど工夫を凝らしても売れないものです。不良品や破損品も含まれます。

倉庫の中には、いつ仕入れたか分からないくらい古いものや、売れる可能性が無いもの、季節商品、モデルチェンジによる売れ残り品などが眠っている場合があります。
それらの価値は、下がることはあっても上がることはないでしょう。
むしろ、本来の価格では売れないにもかかわらず倉庫の場所を取り、管理費を発生させます。
保管しているものは経費にもならないため、税金にも影響します。
資産というよりも、お荷物でしかありません。
貸借対照表の商品は、本当に価値があるのでしょうか?
数字だけでは安易に判断ができないということをおさえておきましょう。
商品管理はできているか?
貸借対照表の商品は、売りに転じるものとしてあたかも会社の資産のように見えますが、
滞留在庫が管理されず適当になっていると、実際の商品価値と貸借対照表の商品の額にどんどん差額が生じてきます。
滞留在庫があるか無いかは、その会社の内部でなければ分からない場合もありますが、損益計算書を見ることで気付ける場合もあります。
見るべきは、損失の計上です。
売れる可能性の無い商品を処分したり、適正な価格で評価しなおしている場合、滞留在庫は商品除却損失や、商品評価損という形で損益計算書に計上されます。

このように、貸借対照表の商品は、額面通りに受け取れない可能性もあるため、注意が必要です。
商品がきっちりと管理されている場合は、貸借対照表に計上されている商品は適正な価格であるといえます。
滞留在庫が都度整理されているか、確認しましょう。
経営分析の基本:売上債権は要注意!

売上債権には注意が必要
資産を見るうえで特に注意したいのが、流動資産の売上債権。
売上債権とは
売掛金や受取手形のこと。
売掛金とは、商品やサービスを提供した時に後日代金を受け取る約束として、「掛け取引」において生じた未収代金のことです。
受取手形は、取引の相手先から発行される「為替手形」および「約束手形」のこと。
支払期日になると金融機関で額面金額を受け取ることができます。
あとからお金を回収する売上債権。
本当にお金は回収できるのでしょうか・・・
回収できない可能性がある売掛債権
相手先の会社が経営不振に陥っている場合、中には本当にお金が回収できるかどうか怪しいものも含まれていることがあります。
万が一、相手先が倒産した場合には、「貸倒れ」となり債権金額を回収できなくなる場合があります。
売上は上がったのに現金が入ってこない・・・となると、
会社にとっては大きな痛手です。
貸倒れまでいかなくても、先方都合で売上債権の回収が遅れると、予定していた資金の入金がなく、利益はあがっているのに手元にお金がない!ということがおきます。
黒字倒産を招きかねない大変危険な状態です。
危険性が計上されているか?
では、これらのリスクを会社はどのように管理しているでしょうか。
売上債権の回収が難しいと見込める場合、会社は「貸倒引当金」という科目で、回収の見込みがないと思われる金額を設定し、売掛金や受取手形を減額させます。
貸倒引当金を設定することで、貸借対照表上に売上債権のマイナスが計上され、資産の実際の価値に近づけることができます。
売上債権の額に対して、貸倒引当金の設定額の割合が多い場合は、相手先の経営不振のあおりを受ける可能性があるといえるでしょう。
売上債権に実際の価値が本当にあるか否かを、しっかりと見る必要があります。
経営分析の基本:固定資産を疑え

固定資産に価値があるのか?
固定資産には、減価償却という形で価値の減価をきちんと表示しているものと、価値の減価が表示されないものがあります。
土地については、時の経過や使用によって価値が下がるものではないため、減価償却ができない資産です。
土地は、周辺事情の変化、地域の政治情勢や都市開発などにより値段が変動し、大きく価値が下がる場合があります。
しかし、価値が下がっていても貸借対照表に価値減少分は表示されません。
つまり、貸借対照表に計上されている金額のとおりに資産価値がある!とはいえないのです。
土地が担保になっている場合
もしも土地の評価額が下がっている場合であっても、会社自体が順調に回っていればなんら気にする必要はありません。
土地は、売って初めて損失を認識するため、評価額が下がったからといってわざわざ損失を計上しなくてもいいのです。
気を付けるべきは、土地が借り入れ金の担保に入っている場合です。
金融機関から資金の融資を受ける場合、返済の保証として土地を担保に入れることがあります。
土地が担保に入っていると、それを勝手に売って現金に換える事はできません。
そして、借入資金が返済不能となった場合には、その土地は金融機関に回収されてしまいます。
担保に入っている土地が、売上に影響を及ぼすようなところであれば、会社の存続にも関わってきます。
担保に入っている土地かどうかを調べることも会社を深読みするうえでは重要なことです。
建物についてもおなじことがいえます。
建物は、減価償却という形で価値減少を表すものの、その数字は理論上のものであり、実際の価値どおりに表示されているとはいえません。
実際に評価してみたら貸借対照表の金額と大きくかけ離れていた…ということもあります。
固定資産が本当に価値があるか否か、過信することなく見る必要があります。

&nbs
まとめ
貸借対照表はその会社の財政状態を表します。
しかし、そこに表示されていることがすべてではありません。
貸借対照表に記載されている資産は、必ずしもその金額と同等の価値があるとは限らないのです。
それを見極めるためには、貸借対照表の中での動きや、損益計算書との照らし合わせも必要となります。
経営分析という目線で斜め上から疑い、探り、深読みしてみてはいかがでしょうか。