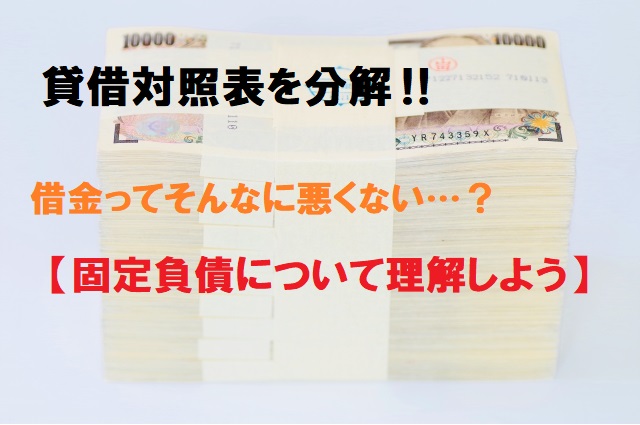こんにちは、 SunnyBizコンサル です。
企業は様々な活動を行う中で、時に金融機関などから借り入れを行うことがあります。
借りる金額は、数千万から億を超える場合と企業によってさまざまですが、個人では想像できない程の多額の借り入れを行う場合もあります。
こんなに借金がある会社だけど、大丈夫なの?なんで潰れないの?
そんな疑問を抱く方もいるかもしれません。
時々、クライアントの方からも「うち、これ以上借りても大丈夫かな?」というような相談を受けることがあります。
それは、負債の特徴をしっかりと理解し、貸借対照表のバランスを読み解くことができれば、きちんと判断できるようになります。
今回は、企業が支払う義務のある負債の中でも、長期的な支払い項目となる固定負債について詳しく解説します。
ポイントはコチラ。
- 貸借対照表の構成を知る
- 固定負債とはどういうもの?
- 固定負債(借金)は悪いことではない?
貸借対照表の構成

概要
貸借対照表は、企業が決算書を作成した時点での財産、債務と、返す必要のない元手資金を表しています。
左側には現金・預金、その他の財産など資金の使いみち、
右側には、資金をどのように集めたか、その内容によって借入金と元手資金が記載されます。

貸借対照表についての詳細はコチラ↓↓↓
貸借対照表を見れば、その企業の懐事情が分かります。
貸借対照表の構成
左側に記載される現金等・その他の財産を総称して「資産」と言います。
右側に記載されるもののうち、いずれ返済する必要のある借入金などの資金を「負債」、返済する必要がない元手資金を「純資産」といいます。
貸借対照表に記載される資産、負債、純資産は、それぞれ「資産の部」「負債の部」「純資産の部」と区切られます。

貸借対照表はこの図の通り、左側に表される資産の部と、右側に表される負債の部、純資産の部の3ブロックで構成されています。
負債の部の構成
貸借対照表の右側には資金をどこから集めたか?ということが載っており、これを「資金の調達源泉」といいます。
負債の部は、その中で「流動負債」と「固定負債」の2つに区分されます。
流動負債と固定負債は、いずれ返済する必要がある資金であることから「他人資本」と呼びます。

流動負債とは、1年以内に支払期限がくる借金などのことです。
固定負債は、支払期限が1年を超える借金などのことです。
決算日の翌日から1年以内に支払が発生するかどうか?という基準で区分することを「1年基準(ワンイヤー・ルール)」と言います。
また、正常な営業活動から発生する掛け取引(買掛金)や、手形取引(支払手形)は、流動性が高いため「流動負債」に分類されます。

今回見ていくのは、赤枠で囲った「固定負債」の部分です。

固定負債について知ろう

固定負債とは
固定負債とは、1年を超えて返済する債務のことです。
流動負債のように、すぐに短期的に支払う必要がないため、支払いを計画的に行うことができ、ゆっくりと資金を回すことができます。
個人でイメージすると、住宅ローンなどが挙げられます。
住宅ローンは、最長50年というものも出ており、長期にわたって返済計画を立てることができます。
長期的に分割払いとすることで、日々の生活に支障をきたさずに、無理なく返済をすることができます。
無理なく長期的な返済計画を立てることができるため、企業にとっては、流動負債よりも固定負債の割合が大きい方が資金繰りは安定的と見ることができます。
固定負債の種類
固定負債はその内容により3つに分類することができます。
- 長期借入金
- 社債
- 引当金
長期借入金
長期借入金とは、1年を超えて返済をおこなう借入金のことです。
金融機関から借り入れる時は、ほとんどの場合が長期的なものです。
通常、まとまった資金を借り入れるため、一括返済ではなく数年にわたって分割返済を行います。
借り入れたもののうち、1年以内に返済する金額は流動負債の「短期借入金」に計上します。
残りの、1年を超えて支払うべきものが、固定負債の長期借入金に計上されます。
社債
社債とは、企業が発行する債券のことを言います。
企業は、金融機関からお金を借りる以外、投資家などに債券を買ってもらうことで、一時的に資金を集めることができます。
企業は社債を発行すると、購入者へ定期的に金利を支払う必要があります。
これは契約に基づくため、利益が出ても出ていなくても必ず支払わなければなりません。
また、社債は、約束の日が来ると購入者に額面金額を返済します。

社債は、短くても償還日が3年先とかになるため、固定負債に載せます。
引当金
引当金は、将来の支出に備えて準備するものです。
1年以内の短期間に支出があると想定できる場合は流動負債に計上し、もっと先々の支出を見込んだ場合は、固定負債に計上します。
固定負債に計上する引当金で代表的なものに「退職給付引当金」があります。
退職給付引当金は、従業員が退職した際に支払う一時金や退職年金のことです。
企業は、従業員が退職した際に多額の資金を支払うことを想定し、何年もかけて積み立てを行います。
長期間支払う予定がないため、固定負債に計上します。

固定負債の特徴
固定負債は、短期間での返済を想定していないため、ゆっくりと計画的に返済をおこなうことができます。
長期借入金や社債によって集めた資金は、主に、設備などの固定資産を購入するためや、新商品を開発するための研究開発費用に充てられます。
手許のお金自体を分けることは困難ですが、貸借対照表上では、日々の企業活動にかかるものは流動負債、高額な投資物に関しては固定負債とすみ分けることができます。
固定負債を違う視点から見てみよう

固定負債は企業にとって悪なのか?
固定負債のメイン項目は「長期借入金」でしょう。
借り入れと聞くと、借金をする…という悪いイメージを持ちますか?
長期借入金にどーんと数字が上がっていると、この会社大丈夫かな?と思うこともあるでしょう。
しかし、大きな事業を動かす際や、何か新しいことを始めるうえで、周りの力を借りることはとても重要です。
すべてを自社の資金でまかなおうとすると、一歩踏み出したい時にブレーキがかかったり、資金の余裕がなくチャンスを逃してしまうことがあります。
また、ある程度の余裕があるうえで借り入れを行う場合と、ギリギリまで自己資金でやりくりし、資金が底をついた状態で借り入れを行う場合とでは、金融機関からの印象も異なります。
長期借入金は、すぐに資金を返さなくていいため、じっくりと経営戦略・経営計画を立てながら資金を回していくことができます。
社債にしても同様です。
また、将来に備えた引当金は、先々を見据えて計画的に資金を積み立てていくため、リスクを回避するための防衛策といえます。
安定した経営を行うために、固定負債の存在は決して悪とはいえず、企業にとって必要不可欠なものであるといえます。
固定負債は企業の信用力を表す?!
金融機関は、資金の貸し出しを行う際、専門的な目線で慎重に決算書を読みます。
融資した金額とそれプラスの利息がきちんと返ってくるか?という返済能力を見ることは当然ですが、融資の判断には、その企業への期待値がプラスされる場合があります。
事業がうまくいっていなかったり、不安な点があると、銀行はお金を貸してくれません。
また、社債についても、きちんと利息と元本を払ってくれそうな会社でなければ、だれも債権を買ってくれません。
融資を受けることができたり、社債の買い手があるということは、それだけその企業に魅力がある、もしくは信頼があることを表しているといえます。
そのため、借金=悪いものという訳ではなく、借り入れが出来るということは、これだけ借りる企業力がある!と捉えることができます。
借金は悪くない?!けれども…
ただし、借入金は、有利子負債といって、返済時に借入金にプラスして利息を支払う必要があるものです。
社債にしても定期的な利息の支払いがあり、また、期日になったら額面金額を全て返済する必要があります。
借りたお金をそのまま返すだけでなく、そこに利息分が上乗せされるため、利息として出ていった分、利益に影響を及ぼすことになります。
借りる額や借りる期間、利率によって利息額は変わるものの、借入金や社債の発生は、それに伴って経費の発生・現金の減少が起こることを念頭に置いておきましょう。
また、引当金に関しても、先々必ず資金が出て行くものです。
いずれにしても、いつかのタイミングで必ず資金の支出を伴うため、資金繰りには十分な注意が必要です。

要するに資金繰り
借り入れが多いと、この会社大丈夫?と思ったり、これ以上借りて大丈夫だろうか…と不安になることもあるでしょう。
確かに、借入金の残高に〇億…なんて数字があると、少々驚きますよね。
しかし、企業はきちんとお金が流れていれば、簡単に倒産することはありません。
出入りが激しい運転資金をしっかりと回し、過去の投資をコツコツと利益として回収していけば、走り続けることができます。
借入金が多くあったとしても、計画的にお金を回し、資金の動きを止めることなく、健康的に循環させていくことが重要です。
まとめ
負債として抱えるものが少ないことは、企業にとって理想的です。
ただし、負債を恐れて挑戦をためらったり、活動規模を小さくすることは、正しい経営戦略とはいえません。
固定負債は、じっくりと返済計画を立てることができます。
計画的かつ有効な使いみちで、事業を発展させていきましょう。