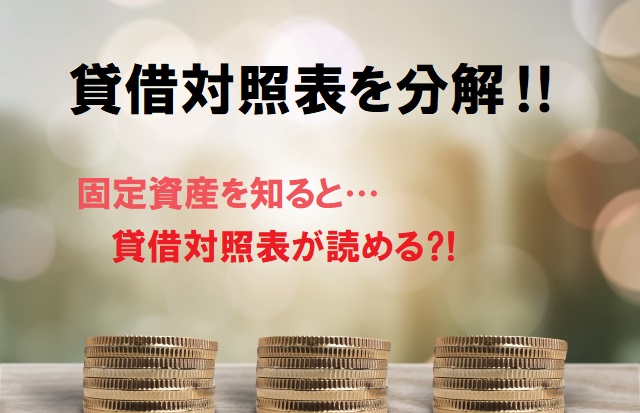こんにちは、 SunnyBizコンサル です。
貸借対照表は、決算書の中でも財務三表といわれる主要なものの1つであり、企業の「お金」に関する情報を明確に表しています。
貸借対照表から情報を得るためには、基礎知識としてどこに、何が、どのように表示されているかを知る必要があります。
今回は、貸借対照表を分解し、資産の部にある「固定資産」に着目して解説します。
ポイントはコチラ。
- 貸借対照表の構成を知る
- 固定資産とはどういうものなの?
- 固定資産にはいくつか種類がある
- 固定資産を知ることで貸借対照表が見える?
貸借対照表を分解し、個別に見ていくことで、貸借対照表を読む際の視点が身についてきます。
貸借対照表読解の基礎知識として、固定資産の理解を深めましょう。
貸借対照表の構成

概要
貸借対照表は、企業が決算書を作成した時点での財産、債務と、返す必要のない元手資金を表しています。
左側には現金・預金、その他の財産など資金の使いみち、
右側には、資金をどのように集めたか、その内容によって借入金と元手資金が記載されます。

貸借対照表についての詳細はコチラ↓↓↓
貸借対照表を見れば、その企業の懐事情が分かります。
貸借対照表の構成
左側に記載される現金等・その他の財産を総称して「資産」と言います。
右側に記載されるもののうち、いずれ返済する必要のある借入金などの資金を「負債」、返済する必要がない元手資金を「純資産」といいます。
貸借対照表に記載される資産、負債、純資産は、それぞれ「資産の部」「負債の部」「純資産の部」と区切られます。

貸借対照表はこの図の通り、左側に表される資産の部と、右側に表される負債の部、純資産の部の3ブロックで構成されています。
資産の部の構成
貸借対照表の左側にある資産の部は、その中で「流動資産」と「固定資産」の2つに区分されます。

流動資産とは、現金そのものや1年以内に現金化される資産のことです。
固定資産とは、1年を超えて長期にわたって保有するものや、現金化するのに1年超の時間が必要となる資産のことです。
このように、決算日の翌日から1年以内に現金化されるかどうか?という基準で区分することを「1年基準(ワンイヤー・ルール)」と言います。
また、正常な営業取引から発生する掛け取引(売掛金)や、手形取引(受取手形)、商品についても、毎月のように発生・回収を繰り返すため、流動性が高いと見ることができ「流動資産」に分類されます。

今回見ていくのは、赤枠で囲った「固定資産」の部分です。
固定資産について知ろう

固定資産とは
固定資産は、長期間使う目的で購入した資産であり、すぐに現金化することができない資産です。
その基準は1年であり、1年を超えて使うものや現金化しないものは固定資産に分類されます。
企業は、固定資産を持つことによって安定的に、長期的に経済活動を行うことができます。
固定資産を購入する時は多額の資金が必要となるものの、それが売上に繋がる価値となり、利益を生み出すきっかけとなります。
現金化せずに持ち続け、使い続けることを前提としているため、固定資産は利益を生み出すための土台になるものといえます。

貸借対照表の流動資産に関する記事はコチラから↓↓↓
固定資産の分類
固定資産は、その中で3つに分類することができます。
- 有形固定資産
- 無形固定資産
- 投資その他の資産
有形固定資産とは、形があって長期間使用するものであり、建物や車、土地などが挙げられます。
無形固定資産は形がないものの長期間使用するものであり、代表的なものがPCなどで使用するソフトウェアです。
投資その他の資産は、経営の維持を目的としたものや、資産運用を目的とした投資などがあります。
3つの固定資産の内容については、次の章で触れていきます。
固定資産の特徴
固定資産は先に触れたとおり、1年を超えて保有し利用していくものです。
そのため、購入時に一時的な費用として全額経費にするのではなく、そのモノが使える期間を見積もって経費を振り分ける必要があります。
これを「減価償却」といいます。
固定資産の特徴は、この「減価償却」にあります。
例えば、建物を購入した場合。
購入する際に現金一括で支払ったからといって、すべてを今年の経費として取り扱ったら…
経費ばかりが大きくなり、売上とのバランスが大きく崩れてしまいます。
それでは適正な利益を計算することができません。
建物は、買ってすぐに消耗されるものではなく、20年、30年と使い続けることができます。
建物の価値自体も、使ってすぐに減るのではなく、年月と共に徐々に減少していきます。
それをしっかりと表すためには、その使用期間で経費を振り分けることが必要です。
固定資産は、買ったその年に大きく売上に反映するのではなく、長期間にわたって使用することにより、売上や経営に貢献していきます。

減価償却をする固定資産は、最初に購入した時は資金が減るものの、それ以降は費用として経費があがるだけで、資金自体は支出がありません。
経費があがってもその分手許にお金が残るため、減価償却は、ゆっくりと資金を回収していると見ることができます。

固定資産に載る主なもの

有形固定資産
有形固定資産は、その文字どおり形があって、目に見えるもので、長期にわたり保有・使用するものです。
主なものは次のとおりです。
- 建物
- 車両
- 機械装置
- 土地 など
販売目的で所有するものは除きます。
無形固定資産
無形固定資産とは、形こそないものの、価値があるものを意味します。
主なものは次のとおりです。
- 特許権(新しい発明を行った者に与えられる権利)
- 商標権(ロゴなど、商品を区別するための文字・図形などを独占的に使用できる権利)
- 意匠権(デザインを独占的に所有できる権利)
- 著作権(文芸・学術・美術・音楽などにかかる利益を独占する権利)
- のれん(見えない企業の収益力のこと。営業権ともいいます。)
- ソフトウェア(PCなどで使用するアプリケーションなど)
- 電話加入権(電話回線の契約権利) など
無形固定資産は、目に見えない資産です。
しかし、企業が業務を行ううえではプラス要因となることから、資産として取り扱われます。
投資その他の資産
投資その他の資産は、ほかの企業への投資に関するものと、長期の資産運用に関するものと、その他のものがあります。
具体的には以下のとおりです。
- 投資有価証券
- 子会社株式
- 出資金
- 長期貸付金 など
また、有形固定資産と無形固定資産に分類されない資産もここに載ってきます。
売却・回収することによる利益を目的としたものではなく、持ち続けることで企業になんらかの価値をもたらすものとして、長期的に保有し続けるものです。
資産の部を二つに分ける理由

流動資産と固定資産を分ける理由
同じ資産であるにもかかわらず、資産の部を流動資産と固定資産に区分するのはなぜでしょうか。
その理由は、大きく2つ挙げられます。
- 現金化のタイミングを把握するため
- 資金の特徴が異なるため
以下、詳しく見ていきます。
現金化のタイミングを把握するため
ひとつは、現金化のタイミングを正しく把握するためです。
流動資産は、1年以内に現金化するものが集計されます。
固定資産は、1年を超えて保有・使用されるものが集計されます。
これらを明確に区分することによって、貸借対照表から現金化のタイミングを知る事ができます。
企業にとって、現金は血液ともいえる重要なものです。
貧血になったり、ドロドロに滞ったりすると、企業にとって大きなリスクとなります。
健康的に資金が循環を繰り返しているか?
きちんと現金化されているか?
お金を動かす能力(支払い能力)があるか?
という点を見るために、資産の部を区分することは重要です。
資金の特徴が異なる
もう一つの理由は、資金の特徴にあります。
流動資産に載ってくるものは、日々の企業活動とともに常に動きがあるものばかりです。
事業を行うための活動資金として、絶えず増減を繰り返す資金のことを「運転資金」といいます。
運転資金は、モノを仕入れたり、従業員へ給料を支払ったり、事業を順調に進めるために重要な資金です。
「運転資金」に対して、固定資産に載ってくるものを「設備資金(または固定資金)」といいます。
固定資産に載ってくるものは、すぐに現金化されるわけではなく、事業を維持・発展させるために持つものがほとんどです。
一見すると現金化のイメージは沸かないかもしれません。
しかし、固定資産の中でも減価償却される資産については、減価償却費として経費処理されるタイミングではお金が出ていかないため、その分だけ資金を回収していると見ることができます。
経費処理することで利益は減るけれど、資金は動きません。

このように、資産の部を流動資産と固定資産に区分するのは、資金の性質が関わるといえます。
固定資産から貸借対照表を読む

事業の特徴を読む
固定資産の内容には、その企業が行う事業の特徴があらわれます。
例えば製造業。
製造業は、工場や機械を活用して事業を行います。
そのため、固定資産には、建物・機械・器具備品・建物を建てるための土地などが載ってきます。
Webサービスを展開するような企業の場合はどうでしょうか。
無形固定資産であるソフトウェアや、権利に関するものが載ってくるでしょう。
その他にも、業種によっては車両を多くもつものや、権利金・保証金を持つものもあります。
固定資産を見ることでその業種の特徴を知ることができるため、貸借対照表を読む視点のひとつとして活用してみましょう。
将来性を予測することができる
固定資産を見ることは、企業の将来性を予測するうえで重要です。
企業は、前提として永続的に事業を行っていくものであり、長く続けていくためには企業努力が不可欠です。
企業の努力は、積み上げられた利益の有効な活用に表れてきます。
資金を設備投資に回したり、その他の投資へ回している場合は、その企業は今後ますます発展する可能性があると見ることができます。
固定資産の増加は、企業の将来性・成長性を予測する判断材料になります。
ただし、固定資産ばかりが膨らみ、流動資産が少なすぎる場合は、決して良いとは言えません。
特に、流動資産よりも流動負債が多い場合は要注意です。
すぐに受け取れるお金よりも支払いに回すお金の方が多いため、資金繰りが悪くなります。
固定資産だけでなく、流動資産と流動負債のバランスもしっかり見ておきましょう。
資金の運用状況を見ることができる
貸借対照表の資産の部は、調達してきた資金がどのように使われているかを表しています。
現金・預金以外は、一見するとお金のイメージとは離れますが、企業が持つ財産は、どんな姿のものであっても、もとは現金です。
土地や建物は、現金が形を変えたものです。
購入した場合は、資産の部の流動資産にある現金・預金が減って、固定資産の土地や建物が増加します。
売掛金が多くあがっている場合は、その売上をあげるために多くの材料を現金を使って購入したことが推測できます。
このように、直接現金の動きが見えなかったとしても、資産の部の数字の動きを見ることで、調達してきた資金がどのように使われているかを予測することができます。
まとめ
貸借対照表の固定資産を知ると、企業の特性や状態、将来性などが見えてきます。
より正確な情報を得るには、さらに細かく数字を交えて分析する必要があるものの、基本的な部分をおさえていれば、企業の全体像を把握することができるでしょう。
情報をしっかりと読み取るために、理解を深めていきましょう。