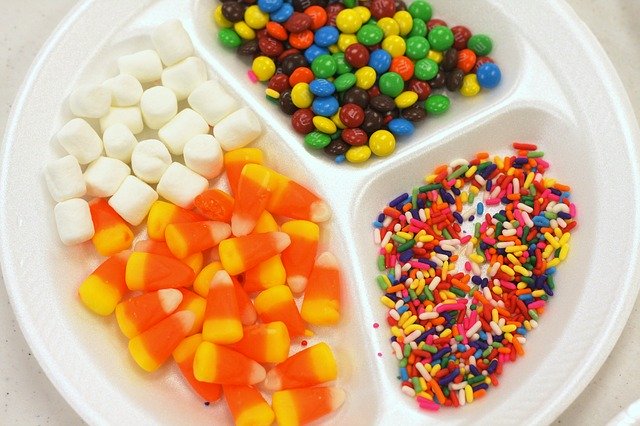こんにちは、SunnyBizコンサル です。
今回は、STP分析の中の S=セグメンテーションについて掘り下げて解説します。
STP分析は、販売戦略を立てる際に活用する大変重要なフレームワークです。
STP分析を行う手順は、英語の並び通りS(セグメンテーション)⇒T(ターゲティング)⇒P(ポジショニング)です。
SとTとPの理解を深めることで、STP分析を効率よく進めることができ具体的な戦略を立てる際に役立ちます。しっかりと理解していきましょう。
■STP分析の全体像を掴むにはこちら↓↓↓
セグメンテーションとは、自社の活動する領域(市場)を決めるためのものです。
STP分析を始める際には、最初にセグメンテーションを行う必要があります。
この記事ではまず、
セグメンテーションの概念と必要性について触れます。
次に、実際にセグメンテーションを行う際の分析指標について、具体例を入れて説明します。
最後に注意点を指摘し、全体をまとめます。
この記事を読むことで、セグメンテーションの概念と手順を理解することができ、次のT=ターゲティングの手順にうまく繋げることが出来るようになります。
企業にとって重要なフレームワークであるSTP分析の取り掛かりとして、セグメンテーションの理解を深めていきましょう。
セグメンテーションとは?

セグメンテーションの概念(Segmentation)
セグメンテーションとは、「分割する」という意味があります。
マーケティングにおいては、市場を細分化するということを意味します。
セグメンテーションを行う目的は、ニーズが類似している顧客を細かくグループ分けし、市場全体を整理するためです。
これは、新市場の開拓や、新商品の開発をするとき、あるいは既存商品の販売対象を再検討する際などに、市場のどこにニーズがあるかを探るために行います。
市場を細かく性質ごとに分割整理することで、その性質にあった商品・サービスを提供することができ、顧客ニーズに合わせた販売活動を行えるようになります。
結果、セグメンテーションを行うことで、自社の活動領域を決めることができます。
セグメンテーションの必要性
セグメンテーションが必要とされる理由は、無駄な販促活動によるリスクを避け、費用対効果の高い戦略を行うためです。
今の時代、顧客のニーズは多様化しているため、すべての顧客を対象に販売戦略を立てることは効率的ではありません。
それぞれの性質ごとに分割し、そこにフォーカスを当てて戦略を立てていくことで無駄がはぶけるため、セグメンテーションは重要です。
特定の細分化された市場に集中してマーケティング活動を行い、無駄なく確実に利益をあげるためには、土台となるセグメンテーションは必要不可欠といえます。
セグメンテーションから次のターゲティングへ移る際に、ターゲットをイメージしやすくするためにも、しっかりと活動領域を定めましょう。
セグメンテーションの分析指標の活用

セグメンテーションを行うには、似たようなニーズを持つ顧客層に分けて市場を細分化する必要があります。細分化するには、4つの分析指標を使って行うことが有効的です。
- 地理的変数
- 人口統計的変数
- 心理的変数
- 行動変数
これらの指標を使い、市場のニーズを把握し、市場を細分化します。
地理的変数・人口統計的変数・心理的変数は、顧客の特性を表すものであり、行動変数は消費行動の特性を表すものです。
特性を見極めて分割するか、消費者の行動を意識して分割するか、もしくは両方を加味するか考えながら細分化するグループを考えましょう。

以下、4つの分析指標について詳しく説明します。
地理的変数
地理的変数によるセグメンテーションとは、国・地域、人口密度、気候、宗教、文化などの地理的な要素による分割をいいます。
例えばコンビニの場合。
コンビニは、市場を「オフィス街」と「住宅街」に分割し、それぞれの立地に品揃えを変えています。
これは、地域・立地・来店する人の属性によってニーズが異なることに着目し、市場を分割しています。
他にも、加工食品市場では、販売する地域によってダシの味を変えている例があります。
有名なところでは、日清が販売しているカップ麺『どん兵衛』です。
『どん兵衛』は、蓋の部分に東と西を区別する(E)と(W)の文字を記し、東(E)と西(W)でスープと、おあげの味を変えています。
ダシの材料が異なるため、スープの色についても東は濃く、西は薄いのが特徴です。
市場を西と東にセグメントし、それぞれの地域の食文化に合った商品を販売しています。

他にも、衣料品を扱う企業においては、北の方と南の方では、卸す洋服の種類が異なります。
このように地理的な要因で市場を分割することで、その地域に合ったマーケティング戦略を立てることができ、その場所に適した活動を行うことが可能になります。
web商材や、ネット通販など、場所を限定する必要がない場合には、地理的変数による分割は行わなくてもいいでしょう。
人口統計的変数
人口統計的変数によるセグメンテーションとは、年齢、性別、職業、所得、学歴、家族構成など、人そのものを属性ごとに分割してデータをとる方法です。
情報収集の方法例にコンビニのレジ打ちがあげられます。
コンビニではレジ打ちの際、顧客に関する情報を打ち込むというマニュアルがあります。
顧客の見た目によって、〇代男性、〇代女性という年代・性別をボタン入力しているのです。
本部はこれを集計することで、どんな年代がいつ何を買うのか?という情報を得ることができ、市場の動向を知ることができます。
この情報により、来店する顧客の属性に合わせた商品をそろえたり、仕入れの量を調整したり、データに基づく戦略を考えることができます。
人口統計に関する資料は、公的機関の調査データや、統計局のデータを見ると良いでしょう。
統計局のHPを見ると、色々なデータを得ることができます(参考URL//統計局HP)。
これを見れば、企業がいちから探求活動をしなくても、おおよそのデータを入手することができます。
調査会社が行うアンケートの結果もネット上で公開されていたりするため、自社に必要なデータをネット等で検索し、それを参考にするのも良いでしょう。
心理的変数
心理的変数によるセグメンテーションとは、価値観、趣味、嗜好、ライフスタイルなどをもとに市場を分割するものです。
人の属性である、年齢・性別・年収などで分割した場合、それだけの切り口では市場を細分化した…とまでは言えない場合があります。
そこに、趣味・趣向・価値観をプラスすると、より具体的に市場を絞って分割することができます。
例えば、「20代・女性・大学生」だけで区切るよりも
- 20代・女性・大学生・ギャル系
- 20代・女性・大学生・キレイ系
- 20代・女性・大学生・カジュアル系
と、いうように年齢・性別・職業だけでなく、趣味趣向も考慮して市場を分けた方が、そのグループごとのニーズを把握しやすいです。
顧客の購買意欲を引き出すために、顧客のニーズが類似するグループに分けるようなイメージで市場を細分化してみましょう。
行動変数
行動変数によるセグメンテーションとは、購買の頻度、パターン、反応などを要素として分割するものです。
たとえば、学習を例にあげると、オンライン・教室通学・個別指導・独学(本)・Web教材など、学ぶ方法についてのニーズは多様化しています。
そこで、顧客の学ぶ頻度、形態、継続性などの行動データから、市場を分けます。
(例)資格取得に関する販売を市場にしようと検討している場合
- 週2回、オンライン配信、3か月で資格を取得する
- 月1回、Web教材を自宅へ郵送、1年かけて資格を取得する
- 週末、教室通学、短期合格を目指す など
顧客ニーズとして、どのような内容のものが、どれだけの頻度で、どのような方法によってどのくらいの期間で行われるか、その好みの傾向が分かると、販売する商品との結びつけもイメージしやすいです。
日用品の場合は、レジにPOSシステムが採用されており、それにより顧客の情報は集約されます。
先に触れた、年代・性別を打ち込むコンビニのレジもその一つです。
「いつ、どの店で、どの商品が、いくらで、何個売れた」という情報をPOSデータで管理することにより、消費者の購買行動を知ることができます。
ネットの購入履歴に基づくデータも、ヘビーユーザーかライトユーザーかを判断する材料になり、消耗品の買い替え時期やパターンが分かるため、購買行動を知る大切なツールです。
分析指標 まとめ
| 分析指標 | セグメントの変数内容 | セグメントの具体例 |
| 地理的変数 | 居住地域・国・文化・気候・人口密度・生活習慣・宗教など | 都市部か郊外か、関東か関西か、日本か外国か、年間気温・気候の変化、湿度…など |
| 人口統計的変数 | 性別・年齢・職業・所得・家族構成・学歴など | 老若男女、独身・既婚、子供がいるかいないか、学生か社会人か、サラリーマンか自営業か…など |
| 心理的変数 | 価値観・ライフスタイル・趣味趣向・性格など | 高級志向か節約志向か、ブランド志向かノーブランドか、インドアかアウトドアか、外交的か内向的か、デジタルかアナログか…など |
| 行動変数 | 購買頻度・購買パターン・セール反応など | ヘビーユーザーかライトユーザーか、セール時の反応が強いか弱いか、定期購入か否か、朝・昼・夜…など |
セグメンテーションは、この4つの指標すべてを使って行う必要はありません。
自社の活動領域を決めるための手順として、属性にとらわれすぎず、顧客のニーズが最も把握できそうな指標を選んでセグメンテーションを行いましょう。
セグメンテーションの有効性の確認
セグメンテーションがきちんとできているかどうかは、次の点で確認することができます。
①測定可能性
規模、ニーズ、満足度が測定できるか
②到達可能性
販売経路や、顧客対象にきちんとアクセスできるか
③維持可能性
継続して利益が上げられるほど十分な市場規模があるか
④実現可能性
効果的なマーケティング戦略を立案できるか、マーケティング活動を実施できるか
これら4つが明確に見える場合には、その分割した市場はきちんとセグメントされているといえます。
セグメンテーションを行う際の注意点

セグメンテーションを行う際の注意点は以下のとおりです。
細分化しすぎない
市場を細分化することは、ターゲットとの紐づけがしやすくなるものの、あまりにも細かく区切りすぎると市場が小さくなりすぎてしまいます。
一つの領域に絞ってマーケティングを行うことも重要ですが、範囲を絞りすぎると市場の獲得機会を狭めることにもなります。
売上・利益の規模を確保するためにも、細かすぎず、ある程度幅を持たせた共通項で分割することをオススメします。
ニーズに基づく分割を意識する
市場を分割する際、最初に分割しやすいのが「年齢・性別」です。
ただ、男女を10代~60代で区切った場合には、それぞれ6個ずつ市場があることになるため、全部で12個のセグメントができてしまいます。
その12個のセグメントがどんなニーズを持っているか…ということを考えた際、同じ年齢と性別だけの区分では、同年代でもニーズは大きく異なる可能性があります。
「年齢・性別」を要素に入れることは良いですが、より明確に市場を分けるためには、ニーズに基づく分割を意識してセグメンテーションを行うことが重要です。
ニーズに基づく分割ができていると、ターゲットも定めやすくなります。
思い込みを避ける
市場を分割する際に、「~だろう」という思い込みや、予測による分割は避けましょう。
特に、データをもとにして分割できるものに関しては、統計情報や集計に基づくデータをきちんと取ったうえで市場を見ます。
データによっては、季節や気候によって変わるものもあるため、一度取ったデータが正しいと決めつけることなく、都度データを取り直すことも重要です。

まとめ

スーパーやコンビニ、ドラッグストアに行くとメーカーごとに類似した商品が多くあります。
その中でどれを選ぶか?その判断基準は顧客の中にあります。
ただ、顧客がこれを選ぼう!!と判断する時の思考は、企業が作ることも可能です。
自社の活動する領域を決め、そこにマッチする商品・サービスを提供することが出来れば、顧客から選ばれる対象になります。
大切なのは、自社のマーケティング戦略を立てる際、適した活動領域がどこにあるか?という土台を考えて分割を行うことです。
その分割が、次の手順であるT=ターゲティングに繋がります。
まずは、自社の活動領域をどこに定めるべきか、市場をしっかりと細分化しましょう。
そして、その領域のニーズを読み取り、次のターゲットを捉えていきましょう。