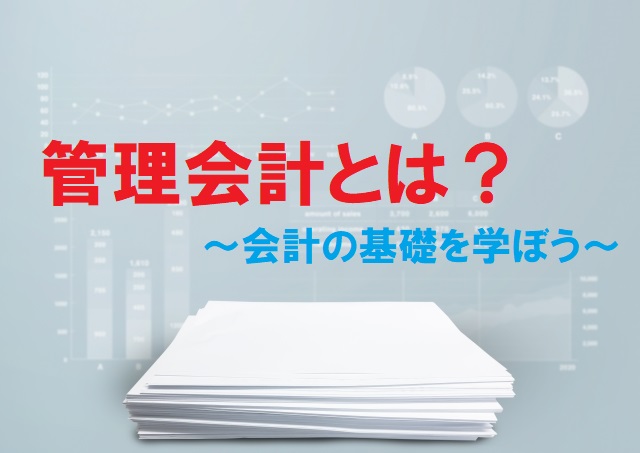こんにちは、 SunnyBizコンサル です。
事業を営む上で必要とされる「会計」。
会計は、日々の経済活動を収入と支出に分けて記録し、集計し、報告するツールとしてとても重要です。
会計とひとことでいっても、企業が関わる会計がひとつではないということ、知っていますか?
会計(=企業会計)は、誰に何を報告するのか、何に使用するのかという目的に応じて、「財務会計」と「管理会計」の2つに分けることができます。
会計についての詳細はコチラから↓↓↓
財務会計についての詳細はコチラ↓↓↓
今回は、会計の基礎知識として企業が関わる会計のうち「管理会計」について詳しく解説します。

管理会計

管理会計とは
管理会計とは、経営者の意思決定に役立つ情報をとりまとめた、内部報告用の会計です。
財務会計は、一定のルールに従い日々の取引を集計していきますが、管理会計には特に厳密なルールはありません。
日々の取引をまとめた帳簿から、より経営の実態が分かるように、数字を分類したり、加工を行い、経営判断に役立てます。
会計の期間は必ずしも1年ごとに区切る必要はなく、月単位、場合によっては週単位で数字を集計し、細かな業績を把握したり、分析することに活用します。
管理会計の特徴
管理会計は、期間ごとに売上やコストを比較・分析したり、来期以降の目標数値を作ったり、現状から未来へ向けた経営判断に役立てるために活用します。
先に触れたとおり、特に厳密なルールが無いため、有用と考えられる全ての財務諸表、取引書類、報告書、集計データなどを利用します。
その特徴は、タイムリーな情報と利益分析です。
タイムリーな情報
管理会計では、主に「月次決算」という、月ごとにしめた数字を使います。
経営者は、日々売上や費用などの状況を知り、必要があれば問題解決に動いたり新たな戦略を打ち出したりするため、経営判断に有用な情報を得る必要があります。
タイムリーな情報として会社の状況をいち早く知るためには、月ごとの数字を把握する月次決算の実施が有益です。
利益の種類
もう一つの特徴が利益の種類です。
利益は、計算する内容によっていろいろと意味が異なります。
事業に関する利益なのか、会社の活動すべてに関わる最終的な利益なのか、その他にも項目を分けて計算することにより利益には色々な種類があります。
管理会計で重要と考える利益は「限界利益(げんかいりえき)」といわれる利益です。
限界利益とは、売上から売上に直接結びつく経費を引いた後の利益です。
売上に直接結びつく経費の例では、材料費・外注費・販売手数料などが挙げられます。
要するに、売上の増減に連動する費用の部分です。

そもそも、売上から売上にかかる費用を引いて赤字であると経営が成り立たないため、まずはこの限界利益がきちんとプラスで確保されていることがとても重要となります。
管理会計の目的

管理会計を取り入れる目的は、未来へ向けた経営判断・意思決定に役立てるためです。
具体的には、「経営分析」・「コスト管理」・「予算管理」を行うことを目的に活用します。
経営分析
管理会計を取り入れる目的のひとつは経営分析を行うためです。
管理会計は、特に決められたルールが無いため、社内のデータをうまく活用することにより、
「この数字、どこから来ているんだろう?」
「なぜこれだけ利益(もしくは損失)が出たんだろう?」
「先々の数字はどのようになるのだろう?」
「これだけの利益を得るためには、どれだけ売上が必要なのだろう?」
「ここの部門(業務)は赤字になっていないかな?」
など、経営を行ううえでの疑問を数字で分析し、追っていくことが可能です。
財務会計では、1年間の活動の結果が財務諸表によって項目ごとに表示されます。
しかし、すべてが集計された後の売上高や経費では、会社が手掛ける業務ごとに利益が出ているのか、どこにコストがかかっているのか、なぜその数字になったのかを個別に把握することはできません。
そこで管理会計を導入し業務ごとに分類して数字を集計すれば、それぞれの業務ごとで業績を把握することができるようになります。
特に社内で製造部門・販売部門・本社部門など、いくつかの部門を設けているような会社であれば、部門ごとに売上や経費を分類し分析することで、業務ごとの細かな原価や利益を把握することができます。
また、決算を待って数字を追っていては、1年間の活動のあとにしか業績を把握することができないため、直近の状態が分からずリスクに対して遅れを取る場合があります。
そこで「月次決算」を取り入れることにより、タイムリーな情報として会社の状況を知ることができます。
月ごと、年ごとで同じ項目について比較検討をしてみると、会社によっては、季節変動に気付いたり、その月々の特徴に気付く場合があります。
その時々でタイムリーに数字を追うことで、現状を把握できたり、リスクにいち早く気付くことができるため、経営分析を行うツールとして管理会計は必須のものです。
コスト管理
企業が売上をあげるためには、様々なコストがかかっています。
そのコストの中には、原材料のように売上に直接的に関わるものと、人件費のように間接的に関わるものがあります。

コストをその性質ごとに分解することで、どこにどれだけコストがかかっているのか?なぜそこにコストがかかっているか?を可視化することができます。
コストを分解することができたら、その中で異常値がないか、削減できる部分がないかを見つめ直します。
コストを抑えることは利益を上げることに繋がるため、コスト管理を行うことはとても重要です。
予算管理
予算管理とは、あらかじめ予算(計画)を立てて事業を実行し、実績を管理することです。
予算は、前年度の数字をベースに設定することが多いです。
予算(計画)を立てていれば、当初の計画値と毎月の実績とを比較し、なぜそのような差異が生まれたのか、その要因を検討することに役立てることができます。
予算よりも実績の方が良い場合には、新たな挑戦に踏み切ったり、設備投資を検討するなど、前向きな経営判断を行うことができます。
逆に、予算と実績の差額がマイナスに出ている場合は、戦略の改善を行ったり、リスクに備えたり、早期の対策が可能となります。
会社の状況は必ず数字に表れてくるため、管理会計の導入による細かな分析は必須です。
現状を把握・分析することで、今後の経営戦略・意思決定に役立てることができるため、管理会計は、未来会計であるといえます。
まとめ
管理会計を取り入れる目的は、未来へ向けた経営判断に役立てるためです。
経営者・管理者は意思決定を行う必要があるため、財務会計よりも管理会計に重きを置き、有益な情報をフル活用して今後の経営に活かしていきましょう。
管理会計の導入を強くオススメします。